Vol.4
@京都府京都市 Wさん邸
5人家族がのびのびと暮らす進化系京町家
間口4m未満の細長い敷地を上手に生かした唯一無二の家
京都洛中のWさんの家は間口約4mという京都特有の「うなぎの寝床」。
2階LDKを段差のあるスキップフロアにし、限られた土地を有効に生かした進化系京町家です。
土地の力を引き出す設計に実績がある工務店「住まい設計工房」と並走した家づくり体験を語っていただきました。
Text:間庭典子/Photo:伊藤 信

“うなぎの寝床”で京都の工務店を検索。
間口4m未満という京都特有の細長い敷地のWさん邸は、3人の育ちざかりのお子さんが健やかに暮らす町家です。
「母親の実家があったこの地に、いつか家族で住もうと決めていました」と夫の直志さん。子供の頃から遊びに行く機会が多く、なじみがあった京都での家づくりを漠然と意識したのは約10年前。飲料メーカーに勤務する直志さんは当時、神奈川に赴任し、横浜市のマンションに一家で住んでいました。
「家づくりを行うにあたっては、京都と関東で距離があり、全国展開しているほうがよかろうと判断し、当初は大手ハウスメーカーのモデルハウスを巡っていました」。ところが、相談しても京都特有の細長い敷地のような条件はあまり理解されず、希望を伝えても、これは難しい、これはできないという返答ばかり。「こんな家にしか住めないのか…とショックでしたね」と妻の広子さんも振り返ります。
そこで広子さんはネットで「京都町家」「うなぎの寝床」などを検索する。たどりついたのが京都を拠点とする工務店、住まい設計工房でした。
「連絡するとすぐに返信があり、『横浜まで行きます』と当時のマンションまで来てくれ、フットワークの軽さに驚きました」と広子さん。住まい設計工房の社長であり、設計者でもある蘇理裕司さんは、現在の暮らし方、収納状況、家具などを把握してからプランをたてるのが信条。「京都への移住という案件でしたので、どんなご家族がどんなお気持ちでいらっしゃるのかとワクワクしながら向かったことを覚えています。敷地には京都特有の制約があるのは予測していたので、ヒアリング前からいくつかのプランを想定していました」と蘇理さんは語ります。

駐車スペースをスキップフロアに潜り込ませ、
LDKの段差で広さを演出する作戦です!
「肝が据わっているな、と頼りになると直感しました」と直志さんも初対面での蘇理さんの印象を語ります。
その後、蘇理さんは建築予定地へ足を運び、その環境や条件を入念にリサーチし、ファーストプランを2度目の横浜訪問で提案。それは2階全体をLDKとし、1階を駐車スペースや寝室、3階に3つの子供室を並べた配置だった。ゆったりとした屋根裏収納もあり、各子供室には寝る空間となるロフトがあり、縦への空間も有効活用している。



「玄関前を駐車スペースとし、その上のスキップフロアをリビングにしました。続くダイニング、キッチンスペースに段差をつけることで、奥行きのあるのびのびとした空間に見せています」と蘇理さん。キッチン奥の小上がりの和室は、2歳の息子さんの遊び場となっています。「視界を遮る柱や壁は一切ないので、キッチンに立つと司令塔のように2階全体を見通せるんですよ」と広子さんもにっこり。一棟一棟を構造計算し、データに基づく強度が保証されるSE構法により、壁や柱に頼ることなく、自由度の高いデザインが可能となりました。
よく見るとLDKは長方形ではなく、キッチンの前の壁を敷地ぎりぎりまでせり出したゆるやかな台形になっています。構造部分をあえてデザインの一部として見せ、天井を最大限まで高くするなどの設計で、目にも心地の良い3階建ての住まいを目指しました。








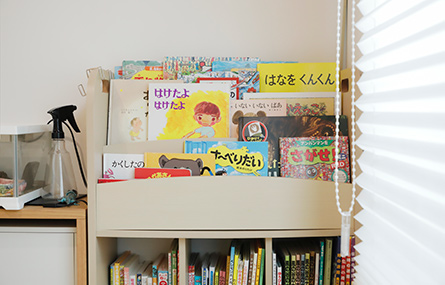

『避難所になる学校の校舎と同等の強度ですよ』
と諭され、木造でも大丈夫だと納得」
デザイン以上に直志さんが重視したのは耐震性です。
「自分たちはちょうど子供の頃に阪神淡路大震災を経験しているので、倒壊した木造住宅などの惨状がまだ脳裏に焼き付いているんです」と直志さん。木造住宅で3階建てがかなうのだろうか、安全性に問題はないだろうかと不安があったそう。
「当時はSE構法についての知識がなく、蘇理さんからいただいた資料やサイトなどで学びました」と直志さんは語る。「蘇理さんに『避難所となる病院や学校の校舎と同じ耐震等級3ですから、ご自宅が倒壊したら避難所も安全ではないですよ』と言われてなるほど、と納得しました」と広子さん。
阪神淡路大震災を機に、耐震性の高い木構造として考案され、全国各地で広まった耐震構法 SE構法ですが、度重なる大地震でも倒壊した建物はありません。
さらに「住まい設計工房が主催する住宅の内覧会にも参加し、蘇理さんとOBOGオーナーとの関係性の良さも安心材料になりました」と広子さん。少数精鋭の工務店のため、伝達のロスがなく、コミュニケーションがとりやすかったのもメリットでした。
「大手には大手の良さがありますが、土地の個性や住むご家族に向きあい、気持ちを寄り添わせた家づくりを楽しめるのが小規模な工務店の特権です。Wさんご夫妻とも対話を続けながら一緒に並走し、敷地条件にマッチした快適な家を提案できたと思います」と蘇理さんも胸をはります。



狭小住宅であるからこそ、大空間が必要
なのだと、住み始めて実感しています
それからはとんとん拍子に進み、2023年6月には基礎工事が完成、8月には広子さんとお子さんたちが京都の仮住まいへと移り、10月に竣工した。「基礎工事の段階では、こんなに狭くて大丈夫? ここに家族5人で住めるの?と心配になりました」と当時の様子を広子さんは振り返ります。上棟時に構造体が現れると空間は縦方向へ広がり、ほっとしたそう。
その段階を目で追ってきたからこそ、気づいたのはムダのなさ。階段周りには構造柱をデザインとしてなじませる、リビングの壁には構造柱の凹凸を生かした飾り棚を設けるなど、構造体を生かしています。



「大空間や大開口という要素は、狭い敷地だからこそ必要なキーワードであることを、住み始めた今、しみじみと感じています。」と広子さん。広々とした空間での生活動線のよさは、暮らしやすさにつながります。それは子供たちにとっても同様。「キッチンのまわりを回遊魚のようにぐるぐる走って遊んでいます」と広子さんは笑う。「このズドーン感はSE構法でなければ実現しなかったですね」。
大きなソファのあるリビングは、直志さんが特に気に入っている場所だそう。「夜はここでウィスキーを味わったりします。隣接した公園の木々が借景となり、春には桜が咲き、ここでお花見もできるんですよ」と満足そうに語ってくれました。
最後に蘇理さんは「設計段階のコミュニケーションの量と質によって、住んでからの満足度が全然違うものになると実感しています。ノーと言うことは簡単なのですが、描いている夢に対して、どうすれば叶えられるかを、自分自身の家を建てるような気持ちで一緒に考えます。土地や立地環境が持っている可能性を最大限追求して、生かし切る工夫を盛り込むと他にはない、唯一無二の住まいとなります。志しているのは、ずっとご家族の笑顔が溢れる心地良い家づくりです」と注文住宅をつくる本質を示してくれた。
W邸 データ
- 家族構成
- 夫婦、子ども3人、
ヒョウモントカゲモドキ - 敷地面積
- 80.31㎡
- 延床面積
- 141.70㎡
- 階数
- 3階建て
- 設計、施工
- 住まい設計工房


