トイレの間取りや位置で、住みやすい住宅になる!?注文住宅の豊富な実例や、失敗しないためのポイントもご紹介

トイレの間取りや位置で、住みやすい住宅になる!?注文住宅の豊富な実例や、失敗しないためのポイントもご紹介のインデックス
朝一番、そして夜ベッドに入る前にも使うトイレ。中には読書をするなど「くつろぎの場」としても使われる場所です。
生活感が見えやすいところですので、いつもきれいにしていたいと思う場所でもあります。そして、生理現象を受け止めるスペースでもありますので、シークレット感をキープしておきたい場であることはもちろんです。
今回は家づくりの際考えたい「トイレの問題」について取り上げてみたいと思います。使いやすさと、プライバシーが両立できるトイレとはどういうものかを解説いたしますので、お役立てください。
1.間取りでトイレをどこに置くかが一番の問題
トイレは排泄に関する場所であるだけに、ニオイや音が気にならない場所に配置したいものです。どの部屋からもアクセスが良いように、とするとダイニングなど家の真ん中の場所に……それは少し考えにくいものです。
特にお客さまを招くことが多いならば、やはりリビングやダイニングそばはやめておくことをおすすめします。相互に気まずいことから、楽しい時間が台無し、といったことも充分に考えられます。
それとは逆に、家の中でのプライバシーばかりを考えてしまうと、玄関のそばが候補に上がるかもしれませんが、これもまた考え物です。宅配などの突然の来客、チャイムの音が鳴ったときにはトイレの中にいたとき、恥ずかしさが先に立ち、出るに出られないということも発生してしまいます。
特定の部屋のそばもまた、音の問題が発生してしまいます。休日などでお父さんがゆっくり寝ていたいのに、朝の子供の「トイレラッシュ」でなかなか眠れない……。そんなこともおきてしまうかもしれません。
また、隣に建っている家との関係性も考えなければなりません。トイレが隣の家の寝室やリビングに隣接してしまうと、意図せず迷惑をかけてしまうこともあるかもしれませんし、日中であっても「用を足しづらい」と感じることが想定されます。
1-1.高齢の方がいらっしゃるご家庭の場合
上記のように、トイレをどこに設置するのかはとてもデリケートな問題です。しかしながら、ご高齢の方が共にお住まいの場合、また今後一緒に住む予定がある場合は、その方の寝室のそばにトイレを置くことは、将来考えられる介護の問題に立ち向かうきっかけを作ってくれます。
ご本人がご健康なうちはご自分で用を足すことができますし、もしもお手伝いが必要になってもスムーズに誘導することができます。
このような目的でトイレを設置するのであれば、まず、バリアフリー(段差をなくす)や、介護をする方が一緒に入ってもスムーズに手伝える、あるいは車椅子で入れるだけの広さを考えておかなければなりません。
また、トイレ内で具合が悪くなって倒れてしまった場合、内開きのドアですと外からとっさに開けられなくなり、救急時の対応が遅れてしまいます。ドアは外開きないしは引き戸にするのがベターでしょう。
手すりはご本人の状態や身長に合わせて取り付けるとよいものですので、後に考えても間に合います。しかしながら段差解消や広さは、家づくりの段階から考えておかなければなりません。バリアフリーに通じた建築士や工務店であれば、廊下やトイレなど広さなどの間取りの面で特に重要なポイントをアドバイスしてくれます。
1-2.階段下は、意外な「穴場」トイレに最適
通常デッドスペースとなってしまいがちな階段下は、思いの外トイレに向いたスペースです。玄関から直接見えない場所(廊下奥)にドアを設ければ、出入りの気配が玄関に影響することはありませんので、有効な間取りといえるでしょう。
1-3.洗面所の横にトイレを設置すれば、水回りが一つにまとまる
家づくりにおける設備設計も重要なポイントです。給排水は出来ればまとめたほうがイニシャルコストも安くなりますし、メンテナンスも一か所にまとまっている方が作業しやすいでしょう。そういった事を考えると、浴室、洗面、トイレは近くに配置した方が色々なメリットが出てきます。
洗面所の近くと言っても、洗面所とトイレを直接つなげてしまうと利便性が下がってしまうので、空間としてはしっかりと区切ってワンクッションを置くことが重要です。水回りをまとめることで動線も短くなり、掃除などの家事も楽になります。
生活の利便性を重視する方にとっては最適な間取りと言えるかもしれませんね。リビングからは見えにくい場所になるため、音や匂いが気にならないのもメリットの一つです。
1-4.リビングの横は廊下を挟めば最適な場所
リビングは家族が一番長く過ごす場所ですから、その近くにトイレがあると便利ですが、気になるのが音や匂いの事ですよね。食事中やリラックスタイムに、トイレに行きたくなったら、例え家族と言え少し気を遣ってしまいます。まして来客時には自分もそうですが、お客様にそういった気遣いをさせてしまうのは申し訳ないですよね。
そんな時は、ワンクッションとして廊下と言う空間を挟んで配置をしましょう。そうすれば、リビングからの動線としては短くて済みますし、扉と廊下という空間がクッションとなり、音や匂いも気になりません。
2.トイレの間取りの失敗例
2-1.位置における失敗例
トイレをどこに配置するかは結構難しい選択になります。と言うのも、どの場所にトイレがあっても、それぞれに便利な点、不便な点と言うのがあるからです。例えば、玄関の近くにあると帰ってきてすぐにトイレに行くには便利だけど、玄関先での来客対応時には行きづらいですよね。
またトイレを家の一番目立たない端に配置した場合は、普段は匂いや音などの心配はありませんが、夜寝てるときに遠くて不便だと思うでしょう。さらに、2階建ての家の場合にトイレが1階にしかないという場合は、その分別の空間が作れるというメリットがありますが、やはり2階で過ごしている時にはわざわざ階段を下りていくという面倒が増えるという事もあります。
自分たちのライフスタイルを良く考えて、メリットとデメリットの両方を知った上で配置を決めるのが良さそうです。
2-2.広さにおける失敗例
また、トイレはそんなに滞在時間が長いわけではないからと、他の空間を広く作ったしわ寄せとして最小のスペースでしか作れなかったという事もあると思います。例えば、トイレのスペースが小さくて収納スペースを作れなかったと言った例もあります。その場合、広さの事だけを考えると勿体ないなと感じることもあるでしょう。
もしトイレが明るく、ある程度広く、快適な場所だったら、とても気持ちがいいと思いませんか。逆に狭くて暗いじめっとした場所だったら、トイレが嫌な空間になってしまうかもしれません。せっかくの新しい家づくりですから、家中快適な空間にしたいですよね。
3.トイレはいくつ必要?
トイレはいくつ必要なのか、という問いには誰も答えを持ってはいません。しかしながら、家族構成によってある程度簡単にイメージできますので、検討ポイントをお伝えします。
3-1.親+子供ふたり
働き盛りの親と子供ふたりとなると、出勤前・通学前の「トイレラッシュ・洗面台ラッシュ」が想定されるでしょう。トイレのみならず、身支度のための洗面台も奪い合いとなることも考えられますので、トイレと洗面台をセットにして間取りを検討したいところです。
そのようなときは、やはり最低でもふたつのトイレが欲しくなるでしょう。洗面台については、横に2台並んだ形式のものをひとつ作るだけでもラッシュを緩和できる間取りとなります。
親が寝起きする1階にひとつ、子供部屋のある2階にひとつとしてもよいでしょう。
3-2.祖父母+親+子供ひとり
いわゆる2世帯住宅であるなら、高齢者に使いやすいトイレ、親や子で使うトイレとで、合計ふたつは必要となるでしょう。先にも触れたとおり、高齢になればなるほど寝室からトイレへの距離が短いほうが使いやすい間取りとなりますし、将来のことを見越して広いトイレが望ましいからです。
まだ元気な親と子は、ごく一般的なトイレでも事足ります。先の例とは異なり、混雑の問題ではなく、使い方の面で「ふたつ必要」ということになります。
3-3.夫婦ふたり
夫婦のみであって、子どもは考えていない場合であれば、ひとつで充分でしょう。しかしながら注意点がひとつあります。「トイレで読書をする」といった“独占行為”がないならば、という条件がつきます。
4.トイレを安全・清潔に使用するための工夫
トイレは、家族と共有する場所であると同時に、基本的にひとりで使う場所です。このことから、安全に、清潔に使えるような工夫をしなければなりません。
4-1.音の問題に配慮する
1階にも2階にもトイレを設置する場合、2階のトイレが1階の寝室の上に来ないようにする間取りとしましょう。というのも、夜間2階のトイレを使用する度、1階寝室で眠っている人の睡眠を妨害することが考えられます。
4-2.風通しの確保
プライバシーを考えるあまり、窓がないトイレになってしまうと、日中も電気のON/OFFが必要となります。ヒートショック対策には窓のないトイレも“アリ”かもしれませんが、やはり清潔を保つためには湿気やニオイがこもらないよう窓が必須といえます。
しかしながら、近隣の家との関係性でどうしても窓を作りたくない場合は、せめて換気扇を用意します。
4-3.明るさの確保
できれば、照明は人感センサー式のものを採用しましょう。毎回のON/OFFに煩わされることもなくなりますし、用を足した後の手でスイッチに触れないことも、清潔な生活の一助となります。また、背の低いお子さんがトイレに入っても、「暗くて怖い」という思いをせずに済みます。
もしもご高齢の方がいらっしゃるなら、暗くなったら自動的にONになる足元灯をトイレの近辺に用意するのが大切です。コンセントに刺すだけで、暗くなったらONになるLEDライトも販売されていますので、そのようなものを活用するのも良いでしょう。
あまり考えたくはありませんが、初期の認知症では「トイレに行きたいけれど場所がわからなくて失敗する」ということもあります。このようなことを避けるためにも、暗くなったら自動で点灯する足元灯をトイレに行く経路にいくつか置いておくのもひとつの方法です。
4-4.掃除しやすい素材と広さ
ノロウイルスなど何がしかの病気が流行したとき、特にトイレ回りは念入りに清掃したいポイントとなります。特に汚物の飛び散りが気になる床や壁は、清掃に使う水分やアルコールに強い素材で作っておきたいものです。
また、実際に隅々まで清掃をするとなると、ある程度の広さが必要となります。狭いトイレでは、手を伸ばして便器後ろの床を拭こうとしても手は届きません。せめて床拭きクロス(使い捨て)をつける清掃用スティックが回るだけの広さは欲しいところです。
4-5.タンクレストイレ+小さな洗面台はどうか
近年、タンクレストイレ(流す水を溜めないコンパクトなもの)が流行しています。見た目にすっきりですし、掃除もしやすいことが特徴です。タンクレストイレでは手洗いができないことから、トイレ内に小さな洗面台を作ることもありますが、充分に考えてからにしてください。
タンクレストイレは文字通りタンクがありません。水道管の凍結時などに「全く使えない」トイレとなってしまいます。タンクがあれば、一度や二度なら使用はできます。また、タンクレストイレの場合、別にミニ洗面台を作ることがありますが、トイレ内での水の飛び跳ねが増え、洗面台や床の掃除の手間が増えてしまう面が否めません。
もちろん、望むスタイルによって“決め手”は変化しますので、何がよいのかはご自分で選択することとなりますが、ここで挙げたメリットとデメリットを理解した上で決定しましょう。
4-6.収納スペースを設ける
トイレの清潔感は、必要なものであっても極力見せないことでも演出できます。トイレットペーパーのストック、清掃に使用する洗剤、女性用のエチケットボックスなども見えないようにすれば、すっきりとしたトイレにできます。
可能であれば、収納はお子さんの手の届かない高いところに設けてください。そうすることで、トイレの洗剤など危険な成分が含まれているものをお子さんから遠ざけることができます。
5.トイレを広く見せる工夫
トイレの配置や、空間の作り方の重要性はお分かりいただいたと思いますが、やみくもに広ければいいというものでもありません。そこで、トイレをゆったりとした気分で、気持ちよく使っていくためにおすすめのポイントを見ていきましょう。
まず広さは、最低タタミ一畳分はあるといいでしょう。そして空間を広く見せるポイントとしては、クロスを明るい色にすることです。白や、柄物であれば小さな柄にすることで、視覚的に広がりを感じます。
また、トイレ本体のサイズを小さいものにしたり、先述のようなタンクレストイレにする等で、空間に対する圧迫度が減ります。さらに窓を付けられると明るくなり広がりを感じます。収納のスペースが取れない場合は壁をくりぬいて空間の有効活用をするといいですね。
6.掃除のしやすいトイレの特徴
トイレは毎日家族が使うものなので、常にキレイで清潔にしておきたい場所です。そのためにはトイレを設計するにあたって、掃除のしやすさというのも非常に重要なポイントです。まずは、トイレの種類と形状について知る必要があるでしょう。
6-1.トイレの種類
トイレの種類は、大まかに3つあります。まずは、タンクと便器が分かれている「組み合わせ便器」。昔からある一般的なトイレはこのタイプで、それぞれがバラバラである事から、修理や交換がしやすいというメリットがあります。
次に、タンクと便器が一体になった「一体型トイレ」。組み合わせ型よりデザインはスッキリとして掃除がしやすい反面、個別に修理がしづらいというデメリットがあります。最後に、タンクがない「タンクレストイレ」。こちらも個別修理が難しいというデメリットはありますが、デザイン面では一番スッキリとしてスタイリッシュで、掃除がしやすいというメリットがあります。
6-2.トイレの形状の選び方
では、この3種類のトイレの形状について、どのように選べばいいのでしょうか。「組み合わせ便器」については、デザインにはこだわらず、機能も基本的なトイレのみでいいと割り切っている方におすすめできます。次に「一体型トイレ」は、ウォシュレットが付属しているので、ウォシュレット必須の方に適していると言えるでしょう。
最後に「タンクレストイレ」は、とにかくデザイン重視の人におすすめします。また、スッキリしたデザインであるため、掃除が簡単な方がいいと思う人にとってもメリットがありますね。トイレを2つ設置する場合はどちらかをスタイリッシュに、もう一方は予算を押さえてシンプルにという使い分けも考えられます。
6-3.壁紙や床材の選び方
床材や壁紙を選ぶ際に気を付けるポイントは、まず、湿気に強いかどうかという点があるでしょう。トイレは湿気が発生しやすい場所ですので、防水性や防カビ効果のあるものを選びましょう。
次に、お手入れのしやすさも重要です。毎日家族が何回も使う場所ですので、頻繁に清掃する事を考えると、掃除がしやすく、汚れがつきにくい素材がいいですね。滑りにくい床材も、安全性を考慮する上では大切です。また、なるべく材料の張り替えなどが発生しないよう、耐久性の高さも見るべきポイントですね。
7.トイレの間取りと風水
せっかく新しい家を一から作るのであれば、風水にも気を遣った家づくりはいかがでしょうか。良い運気が入ってきて、家族全員が気持ちよく暮らせるような家にしたいものです。そこで気になるのが、風水的観点からみたトイレの位置ではないでしょうか。
7-1.中心部分
家の中心部分は、風水的に安定した場所であり、エネルギーの中心でもあります。家相としては、家の中心は、家長の部屋を置くべき大切な場所とされてきました。一方、トイレは不浄なものとされる風水では、家の中心に置くべきではないと考えられています。
また、中心にトイレを配置するという事は、窓を外に向かって設置することができなくなりますので、換気や通風にも問題が生じ、トイレを清潔に保つことが難しくなる可能性もあるでしょう。
7-2.北東と南西
北東の方角は一般的に鬼門と呼ばれ、南西の方角は、裏鬼門と呼ばれます。鬼門にトイレを設置すると男性の、裏鬼門にトイレを設置すると女性の運気に影響があると言われています。
家を設計する場合には通常、日当たりの良い南側、東側、南東の方角にはリビングなどメインの空間を計画することが多く、トイレはどうしても残った場所に設置せざるを得ないという状況もあるでしょう。そのような場合には、清潔に保つように気を付けることが運気を下げにくくするポイントです。
7-3.玄関の近く
玄関は家のエネルギーの入り口であり、風水面からみると、清浄で良い気を取り込む場所とされます。そのため、トイレが玄関の近くにあると、玄関から入ってくる良い気が、乱れる可能性があると言われています。また、2階に設置した場合に、ちょうど玄関の上に配置せざるを得ない場合もあるかもしれません。
このように玄関近くに設置せざるを得ない場合には、観葉植物を近くに置いたり、清潔さを保てるように気を付けることが重要なポイントです。
7-4.色を取り入れる
日本の昔の家屋では、トイレとお風呂は母屋とは別に建てられていました。しかし、これが家の中に組み込まれるようになり、風水的には良くない位置にトイレが設置されることが増えました。快適な住まいを考える中で、しわ寄せがトイレの配置に及んでしまったような状況ですね。
そのような場合には、トイレに取り入れる色に注意してみましょう。例えば北東には白、南西には黄色が、風水的に相性が良く、運気が下がるのを防ぐと言われています。
8.トイレの間取りについてのよくある疑問
ここで、トイレの間取りを決める際によくある質問を見ながら、皆さんの疑問を解決していきましょう。「これが知りたかった!」という質問から、「ここは気づかなかったけど、大切!」と思うようなこともありますので、よく検討してみてください。
8-1.一般的なトイレの大きさはどれくらい?
一般的なトイレは、幅80cm、奥行160cm程度で、大体0.5坪、タタミ1畳分程の大きさだと言われています。ただ、絶対この広さがないといけないという訳ではなく、他の部屋の大きさとの兼ね合いで小さくなってしまう事もあるでしょう。
狭い場合は幅80cm、奥行き120cmで設計されることもよくあります。マンションなどはこのサイズが一般的です。少し大きめの住宅では、余裕をもって、幅120cm、奥行160cmという大きさになる事もあります。
8-2.トイレの間取りはどのように決めればいい?
では実際、どのようにトイレの間取りを決めればいいのでしょうか。まず考えるのは、必要最低限の大きさを把握することです。そのためには、どの衛生機器を入れるかを決めなければいけません。便器はどのタイプにするかで大きさが変わりますし、手洗いをトイレ内に別で設置するかどうかも考える必要があります。
トイレでゆっくりくつろぐという方もそうはいないと思いますが、座った時に膝が壁や扉にぶつかるようでは、落ち着いて用を足すこともできません。家族の体の大きさに合わせて、適正サイズを決める事も大切です。
8-3.平屋の場合、トイレは2つ必要?
2階建て住宅の場合は、ワンフロアに1つずつトイレを設置したいという希望が多いのですが、平屋の場合はどうでしょうか? 1フロアしかないから、トイレも1つでいいのか? というと、問題はそんなに単純ではないようです。そこには、当然、家族構成と平屋全体のサイズが関係してきます。
夫婦2人暮らしのサイズの平屋であれば、トイレももちろん1つでいいでしょう。ただ、平屋であっても4人家族以上が暮らすとなると、朝や食後の時間などを考えた場合、やはりトイレは2つ必要になってくるというのは、イメージできますね。
まとめ:使いやすさと、プライバシーを両立するトイレは間取りが重要
トイレは、家族共有の場所ですが、一方では完全個室となるようプライバシー面での配慮が必要です。この相反する点をクリアするため、間取りはとても重要な問題となります。その上、衛生面や介護など、注意したいことも多くあるのがトイレです。
様々な条件を満たしながらも、シンプルで美しく、それでいてどこかしらに個性を感じさせるトイレの実例をお見せしましょう。
重量木骨の家でも、魅力的なトイレやサニタリースペースは数多くあります。どうぞご覧になってください。

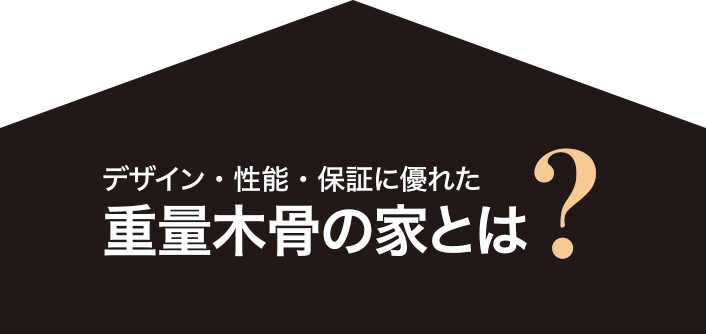






























 はこちら
はこちら