家づくりにおけるパッシブデザインとは? 具体的なデザイン解説から、メリットデメリットまでご紹介!

家づくりにおけるパッシブデザインとは? 具体的なデザイン解説から、メリットデメリットまでご紹介!のインデックス
パッシブデザインとは自然エネルギーを利用して室内環境を快適にする設計手法の事です。自然を上手くコントロールしながら設計することで、断熱効果を高めたり、エアコンや照明器具等の機械を使う量を減らしながら、光や熱を室内に取り入れる事も可能です。そうすることで夏は涼しく冬は暖かい、快適な生活を実現できるのです。今回は豊富な実例も交えながら、パッシブデザインのメリット・デメリットや、具体的な手法等をご紹介していきます。
パッシブデザインとは?

では、パッシブデザインの基本的な考え方とその手法や、パッシブという言葉の元々の意味、さらにパッシブデザインとアクティブデザインとの違いなどをご紹介します。
パッシブデザインの基本
パッシブデザインの基本は、自然エネルギーを有効活用する事にありますが、それを支える3つの重要なキーワードがあります。それは、「断熱・気密・蓄熱」です。機械で強制的に温度を調節しない事を目指しているので、自然から得た暖かい、または涼しい空気を室内に取り込んだら、それを逃さない高断熱高気密の仕様が必要になります。また冬場には貴重な太陽熱を、昼間にたっぷり受け止めて夜までゆっくりと暖め続ける蓄熱も、重要な仕様のひとつです。
パッシブデザインの「パッシブ」とは?
パッシブという言葉は英語のpassiveという単語で、意味としては「受動的、受け身、消極的」等と訳されています。住宅以外にも様々な業界で使われているので、言葉自体には馴染みがありますよね。受動的、消極的という言葉の響きからは後ろ向きな印象を受けそうですが、住宅業界における「パッシブデザイン」というのは、自然エネルギーを受動的に受け止めるという意味ですので、積極的に機械の力で住環境を作り出すより、地球環境に優しく前向きなイメージを感じることが出来るのではないでしょうか。
アクティブデザインとの違い
パッシブデザインに対して、アクティブデザインというものもあります。パッシブが地球環境に優しいのなら、対するアクティブは環境に良くないのでは? と思ってしまうかもしれませんが、それは違います。アクティブデザインもパッシブデザインと同様に、エネルギー消費を抑え環境負荷の低減を目指す手法ですが、自然の力ではなく省エネルギー性能の高い設備を導入することで、快適な住環境を目指しています。パッシブデザインの代表的な設備がルーバーや天窓だとすると、アクティブデザインでは太陽光パネルや発電できる給湯器を設置するとイメージしていただければ分かりやすいかもしれません。
パッシブとアクティブを組み合わせて、快適さと省エネの両方を高いレベルで実現するという選択肢もありですね。
パッシブデザインのメリット
では実際にパッシブデザインを取り入れたいと思ったら、検討する上で、メリットやデメリットを知ることは大切です。パッシブデザインについては、皆さんいいイメージをお持ちの方が多いと思いますので、まずは、メリットについてみてみましょう。
メリット1:冷暖房を減らしても快適な室内環境

パッシブデザインを取り入れると、自然の持つ温熱環境を室内に取り込むことが出来ますので、エアコン等の冷暖房器具の稼働率を下げることが出来ます。例えば窓の位置を工夫することで、風の通りを良くして室内の温度を上げ下げすることが出来ます。
また、天窓をつければ、夏の熱い空気は上に逃がすことが出来ますし、冬の暖かい太陽光を室内に取り込むことも出来ます。これらは、冷暖房器具に頼らなくても出来るパッシブデザインのメリットですね。
メリット2:省エネで光熱費も抑えられる

パッシブデザインは機械に頼りすぎないことで、省エネルギーに繋がります。その結果、光熱費も安くなるというメリットがあります。例えば、吹き抜けと大開口や天窓などを組み合わせることで、例えリビングが北側の1階に配置されていたとしても、たっぷりとした光が上階から差し込みますので、昼間の照明の為の光熱費は抑えることが出来ます。吹き抜けがあることで開放感もたっぷりありますので、さらに明るさも感じやすくなるでしょう。
メリット3:体にやさしく、健康に暮らせる
パッシブデザインのメリットの3つ目としては、体にやさしく、健康に暮らせるということもあります。既にお伝えしたように、窓を開けることで自然の風を家の中に取り込みますので、住んでいる人も自然の風を感じることが出来ます。もちろん真夏の暑い時にはエアコンの涼しい風が快適ですが、当たりすぎて体調を崩すという話も聞かれますよね。そういった意味でもパッシブデザインは、自然の力を利用して快適な空気を感じることが出来、体にも優しいというメリットがある、というわけですね。
パッシブデザインのデメリットや注意点

さて、次はパッシブデザインのデメリットについてもみていきましょう。このデメリットについて許容範囲であるかどうかは、じっくり考えてみる必要がありますね。
建築費が高くなる
パッシブデザインを取り入れるにあたってのデメリットとしては、イニシャルコストである建築費が高くなってしまうという事があります。その理由としては、自然エネルギーから得た温熱環境を、効率よく利用するためには、家全体を高気密高断熱仕様にする必要があるからです。
ただ、家の機能としては建築費が上がる方向ですが、その分内装をシンプルにするなどして全体的な建築費の調整は可能です。また、ランニングコストである光熱費が安くなりますので、トータルで考えると長く住めばそこまでのデメリットとは言えないかもしれません。
土地選びは慎重に
パッシブデザインで家を作る際にとても重要なポイントになるのが、土地選びです。自然からそのエネルギーを取り入れるためには、日照や風の流れ、土地の方角、隣地の環境や風景は将来的にも変わらないのかどうか等、見極めなければならないことが多くあります。
その土地をまず見て、日照や風を取り入れる為、まずは、窓の位置や大きさなどを計画するところからスタートしなければなりません。そこから自然に間取りなどもイメージが出来てくるという感じになるので、自分たちの思い描く暮らしに合う土地なのかどうかと言うのは、初めの段階からよく考えておく必要がありますね。
パッシブデザインの5つの設計手法
さてここまでパッシブデザインについてお伝えしてきましたが、実際パッシブデザインを作るにあたっての具体的な設計手法と言うものが5つあります。その5つとは「断熱、気密」、「日射熱利用暖房」、「日射遮蔽」、「昼光利用」、「自然風利用」と言うものになります。それぞれについて詳しく見てみましょう。
断熱・気密

自然エネルギーを家の中に取り込んで、それによって家の中を快適な環境にするためには、その取り入れたエネルギーが外に逃げないようにするという事が重要になってきます。一般的な木造住宅を考えてみると、住宅と言うのは部材を組み立てて作っていくものなので、その部材のつなぎ目には必ず少しの隙間と言うものが発生します。
そしてその隙間から、室内の快適な空気が外部に逃げていき、外部の不快な空気(夏の熱い空気や冬の寒い空気)が室内に入って来てしまうのです。それらを少しでも防ぐために断熱材や高断熱仕様の窓などを使って高気密高断熱の家にするという事が大事な設計手法の一つです。
日射熱利用暖房

冬の寒い時期に、太陽からの日射熱を取り入れるという事もパッシブデザインの手法の一つです。日射熱をどこから取り入れるのが有効かと言うと、窓から取り入れることになりますので、太陽の光がどう入ってくるかの日照シミュレーションをすることが重要になってきます。そのシミュレーションの結果をもって、窓の位置や大きさなどが決まり、そこから太陽の熱を最大限に取り入れるということです。
また、室内に土間や壁など、コンクリートの面を配置し、コンクリートの蓄熱する性質を利用することもできます。蓄熱する性質から、昼間は太陽の熱を溜めることが出来、気温が低くなる夜には冷たい方へ熱が流れる仕組みから、室内に放熱してくれるというわけです。
太陽の熱を余さずに利用する工夫の一つですね。
日射遮蔽

特に夏場においては、日射量をコントロールすることが室内環境を快適にするうえで重要になってきます。そのために必要なのは、太陽熱を遮断する仕組みです。まずは、庇について。日照シミュレーションを行い、夏は日差しを遮断し、冬には日射を取り込むように庇の長さと位置を決めます。庇の先にすだれを付けるのも有効な手段です。
次に、取り入れやすいルーバーです。可動式のルーバーがあれば、時間帯や季節によってルーバーの角度を調整して日射を遮ることができます。そして、幕のように使うことができるシェード。シェードは、窓の外側に付ける事によって日射を室内まで入らせないようにすることが出来ます。目隠しとしての機能もあり、使わない時には収納できるというのも便利な点ですね。
昼光利用

昼間に太陽の光が家の中まで差し込んで、明るさを感じることが出来れば、照明を付ける必要がありません。パッシブデザインの手法として太陽の光をいかに家の中に取り入れるかという事も重要です。ここでも大事なのは日照シミュレーションになってきます。
太陽の位置だけではなく、近隣の建物の形状や大きさによっても日照は変化します。シミュレーションした結果を元に、リビングやダイニングなど、日中人が集まる場所に太陽の光が長時間取り入れられるように、トップライトや大きな開口部を設計していくといいでしょう。
自然風利用

暑い季節には、出来るだけ外からの涼しい空気を取り入れて、室内のこもった熱い空気は家の外に出したいですよね。自然の風を利用するという事も、パッシブデザインの手法の一つです。では、自然の風を利用するためにはどんなやり方があるのでしょうか。
一番重要になってくるのは窓の位置です。暖かい空気は上部に溜まりますので、家の上部に窓を作ってそこから排出させましょう。逆に外部の涼しい空気は、家の下部に作った窓から取り入れることが出来ます。そうすることで、夏の暑い時期でもクーラーを使う頻度を下げることが可能になります。
パッシブデザインを取り入れた住まいの実例紹介
さてここまでパッシブデザインについてのメリットやデメリット、注意点や設計手法とお伝えしてきましたが、最後に、パッシブデザインを取り入れた住まいの実例をご紹介いたします。色々な実例を見て、自分たちの暮らしに合うものを取り入れてみませんか。
いつでも明るく、風の流れる2階リビング

敷地の条件から、リビングを2階の南側に配置することになったこちらの事例。光を取り込むために大きな開口部を設置し、上にはさらに高窓も設置したことから、日中には太陽の光がLDKに差し込み、明るく開放感のある空間になっています。
またこの高窓を設置したことで南面に将来建物が建ったとしても太陽光を取り込めるようになっています。さらに、東面と西面、北面に対角線上に窓を配置したことで、部屋の中で空気の流れが生まれ、窓を開けているだけで、自然の風の心地よさを感じることが出来るという、パッシブデザインを取り入れています。
蓄熱ルームと可動性ルーバーのパッシブデザイン

外観を見ると、木製ルーバーのデザインが目を惹きますが、これもパッシブデザインの手法のひとつである、可動性ルーバーになります。時間帯や季節によってルーバーの板の角度を変更し、光を取り入れたり、光が入り過ぎるのを防いだりすることが出来ます。
また、LDKの続きに和室があり、その前には蓄熱が出来る仕様の縁側が設置されています。ここは、2重断熱エリアとして、蓄熱をしながら物干しが出来ます。さらにLDKの大きな吹き抜けの一部はグレーチングの床になっており、2階のインナーバルコニーから光と熱をLDKへと届けることが出来ます。
太陽の光を最大限に取り込んだ快適な住まい

敷地が南西に位置し、角度が振れているため陽の入り方は入念に検討が必要だったというこちらの事例は、設計の力によって太陽の光を最大限に取り入れることに成功したパッシブデザインハウスです。
陽の入り方については方角だけではなく、隣地の建物との関係も大切です。その部分をしっかり計算して、配置を隣地の建物より少し前方へずらし、その少し抜き出た部分に吹抜けを設けることで、遮るものがなく陽の入りを確保し、それを階下のLDKまで届くようにしています。吹抜け上部の2階ホールも吹抜け面の大開口から陽の光が届き、第二のリビングとして家族の憩いの場になっています。
最小限の冷暖房で暮らすエコな家

こちらの事例は、パッシブ冷暖システムという、家全体を冷やしたり暖めたりするパッシブデザインシステムを採用し、最小限の冷暖房で暮らすことが出来るようになっている住まいです。このシステムを採用することで、各部屋にエアコンをつけることなく家全体が涼しく、または暖かくなることから、省エネにもつながります。
明るく開放的で省エネも実現した住まい

こちらの事例は、ダイニング上部に吹き抜けを設け、終日日射を実現したパッシブデザインハウスとなっています。ダイニングは1日に2回から3回、家族が集まり食事を取る場所です。家族が一番長く過ごす場所と言っても過言ではないでしょう。そんな一番長く過ごす場所を明るく快適な場所にする事が出来るというのが、パッシブデザインの良いところですね。
また、リビングはダイニングより一段段差をつけることで、仕切り壁をつけずに領域をゆるやかに仕切っています。リビングはシアタールームも兼ねているので、ダイニングルームとは趣向を変えて、天井を板張りにするなど、落ち着いた雰囲気に仕上げています。
風の通り抜けるゼロエネルギーハウス

こちらの事例は、落ち着いた佇まいが印象的な和モダンの雰囲気のあるパッシブデザインの住宅です。こちらの建築会社は、パッシブデザインに特化しており、日照シミュレーションと通風シミュレーションを実行し、窓の位置を決定しています。また設計段階から全棟において室内の温度環境をシミュレーションして、高気密高断熱住宅が設計通りの性能を発揮するかどうかを確認しています。
そういった全てを計算してできたこちらのパッシブデザインハウスは、LDKが南北、東西それぞれの方向に視線が抜ける広々とした空間に仕上がりました。
まとめ
さて今回は、地球環境にも、実際に住まう人にも優しい家づくりである、パッシブデザインについて詳しく見てきました。パッシブデザインとは土地選びから既に始まっており、自然の中の風や光の動きをよく理解し、自然環境を味方につける住まいのあり方であると言えるのではないでしょうか。これから家づくりをする人には、将来の世代交代も見据えて、パッシブデザインの家を選択肢に入れてみませんか。

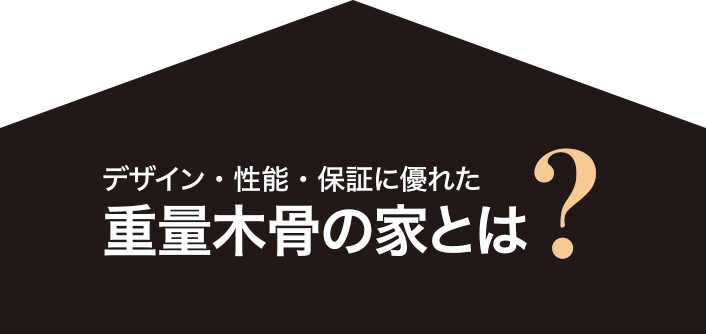






 はこちら
はこちら