こんなに便利!パントリーのある家の、豊かな暮らし方

こんなに便利!パントリーのある家の、豊かな暮らし方のインデックス
皆さんパントリーとはなにかご存知でしょうか。語源は英語で、食品庫やキッチンストッカーとも呼ばれるように、キッチンの脇にあるキッチン周りの収納スペースの事です。毎日暮らしていく中で皆さん感じていらっしゃると思いますが、キッチンは一番生活感が表れやすいところだと思いませんか。せっかく素敵なキッチンを作ったのに収納が少ないためにいつの間にか、モノが溢れる空間に……。という事にならないようにキッチン周りをすっきりさせて使い勝手のいい豊かな暮らしが実現するパントリーを作りませんか。
まずは王道のパントリー
飴色の床と梁が味わい深さを感じるLDKには、オールステンレスで製作したというⅡ型キッチンがその存在感を主張しています。家族全員でこだわり抜いたというキッチンですから、その思い入れの深さが感じられますね。キッチンの奥にみえるのがパントリーですが、食品や食器だけではなく冷蔵庫やオーブンレンジなどの家電を収納できるほどのスペースがあるので、キッチン周りの生活感を隠すことに成功しています。またパントリーの奥には勝手口があるので、家の外へダイレクトにアクセスすることが出来ます。ゴミ捨てや買い物帰りに非常に便利ですね。

I型の長いキッチンの裏には、収納や作業スペースがたっぷりあります。築120年の日本家屋と蔵が建っていた敷地に建て替えたという事で、蔵に収納してあった大量の食器類をしまえるスペースが必要だったそうです。そこで、キッチン背面にこの床から天井までのたっぷりの収納スペースを作り、そこに収めることにしたそうです。ダークな色遣いのキッチンはクールでスタイリッシュな印象を受けますね。さらに奥にはパントリーがありますので、収納の使い分けが自由に出来るというところも非常に便利です。
パントリーには扉がない?
パントリーには扉がないことが多いと思いますが、何故でしょうか。キッチンに隣接して計画され、キッチンで使うものを収納するスペースですので、キッチンから出入りするときに、扉を開けたり閉めたりする煩わしさがないというのがまずメリットですね。また、空間全体としての解放感がありますし、扉がないことで通風の確保もしやすいことから、湿気対策としても有効です。保存しておく食品と言うのは大体乾燥した場所で保管してくださいと注意書きが有るものが多いですから、そういった面からも扉がないことはメリットと言えます。

では、扉があるパントリーにはどんなメリットがあるのでしょうか。やはり、目隠しという機能が最大のメリットです。オープンな作りのパントリーの場合、配置によっては来客時にパントリーの中のものが丸見えという事にもなりかねません。その点扉を付けていればどこに配置するかと言う点で自由度が上がります。また、パントリー内が個室になりますので、一人で過ごしたいと思う時等にも快適に過ごせる空間として使う事が出来ます。湿気の点等はパントリー内に窓を作ったり、来客時以外には扉を開放したりする工夫が必要ですね。
パントリーの魅力はその圧倒的な収納力

パントリーを作る最大のメリットはその収納力の一言に尽きます。一般的なウォークイン型のパントリーの広さは大体3畳くらいが平均だそうです。普段の買い置きの食材や大きな食器類等、収納したいものはたくさんありますし、最近は災害対策として水や非常食の買い置きをする家庭も増えています。その量は水で言うと、大人一人一日3リットル、最低でも3日分は必要と言われていますので、4人家族なら2リットルのペットボトル18本必要となります。やはり、パントリーがあるといざと言う時の準備も出来て安心ですね。

パントリーは収納力も大事ですが、使いやすさももちろん重要なポイントです。大容量だから、ついつい何でも詰め込んで、何がどこにあるか分からなくなってしまったというのでは本末転倒です。 大容量かつ、きちんとオーガナイズできるような棚の作り方をすることが必要ですし、あらかじめ自分の持ち物が分かっている場合はそういったものが入るように計算して棚を作ることも大事ですね。
スペースが足りない時のパントリーの作り方
ウォークインタイプのクローゼットを作るほどのスペースはないけれど、どうしてもパントリーが欲しい場合はどうしたらいいでしょうか。それなら、キッチンの背面のスペースを有効活用して作ってしまいましょう。ウォークインタイプではないので、歩くためのスペースは不要になり、ウォークインタイプのパントリーの1/3位の省スペースでしっかり収納ができるパントリーを作ることが出来るでしょう。目隠しの為の建具を付ければ、見た目はスッキリ生活感を隠すことも出来ます。

キッチンの背面を利用してパントリーを作る時に、壁面を同じ仕上げにせずに敢えて色々な表情を見せるようにするのはいかがでしょうか。見せる収納と隠す収納をうまく活用して、収納自体を空間のデザインのポイントにすることも可能です。また、こちらの事例のように、カウンターを敢えて、キッチンと反対側の窓面に設けることで、キッチン側の生活感が目に入らず、窓からの眺めを楽しみながら食事やお茶を楽しむことが出来るようにするという考え方もあります。
パントリーに別の機能をプラスすると
最近は共働きが当たり前で、家事分担も当然と言った時代になってきましたが、キッチン仕事は女性が担っているという家庭がまだ割合として多いような気がします。それがいいかどうかは別として、キッチン+パントリーが女性の為のリラックススペースになり得ると思うと、なんだか得した気分にはならないでしょうか。こちらは、キッチン横に洗面室へと抜ける通路の役目も担うパントリーですが、その一角には奥様の為の書斎があります。洗面室へ抜ける通路という事で家事動線が考えられれていることはもちろん、本棚とデスクがあるこのスペースは一人になれる素敵な癒し空間と言えるのではないでしょうか。

空間としては、そこまで広い必要はないのですが、やはり一人になって少し考え事をしたり、ホッとする時間があるというのは、いつも忙しく家族の世話をしているお母さんには必要な時間です。例えば座った椅子から明るい外の光を感じるながら、一人でお茶を飲む時間を持てれば、簡単にリフレッシュできそうですね。
パントリー周りの動線を考える
家の中における動線を考えることは、家づくりにおいてとても重要です。ただでさえやることが多いのに、仕事で疲れて帰って来たら、極力無駄な動きはしたくないと思うものではないでしょうか。こちらの事例ではキッチンに隣接したパントリーがウォークインクローゼットと一体になっており、その空間を通路として、洗面、洗濯室へ、さらにその先には室内物干しスペースへと続きます。洗濯して、干して、畳んで、収納までが一動線であり、さらにはキッチンへと続くことで炊事と洗濯までも一動線で済ませることが出来るというパーフェクトな動線と言えるでしょう。

勝手口のあるパントリーも家事動線を考える上で重要です。こちらの事例では、勝手口の三和土部分が広いので、ちょっとした汚れ物なども仮置きすることが出来ます。パントリーの壁にはひっかけ収納やマグネットシートが施されているので、エコバッグ等もさっと収納してさっと取り出しやすくなっています。ふだんの買い物の行き帰りにはこちらの勝手口を使っていれば、エコバッグを忘れることもなく、買って来たものはすぐにパントリーに仕舞う事が出来るので無駄な動きがありませんね。

こちらも、炊事動線と洗濯動線を近くに配置した例ですが、こちらの例ではぐるっと回遊できる動線になっており、直線移動に比べるとさらに無駄な動きが減るような工夫と言えるでしょう。また、家族全員がこの動線を使う事で、みんなで空間を共有することが出来るという事は、家族にも家事の手伝いを頼みやすく、その延長で家族の中で家事分担が自然と進むかもしれません。
まとめ
今回は、パントリーのある暮らしについてご紹介しました。ごちゃごちゃとしがちなキッチン周りの救世主ともいえるパントリーですが、その作り方は様々でした。配置はキッチンと連続した空間と言うのが主ではありますが、絶対そうでなければならないというものでもありません。暮らし方に合わせてそれぞれが使い勝手の良いようにパントリーを配置することが大切です。またスペースがなくとも目隠しを付ける事で省スペースなパントリーを作ることも出来るという事例もありましたし、ひとつのイメージに縛られる必要はないという事をお分かりいただけたのではないでしょうか。あなたと家族の暮らし方に合わせたパントリーを作って、すっきりとした空間で豊かな暮らしを実現しませんか。

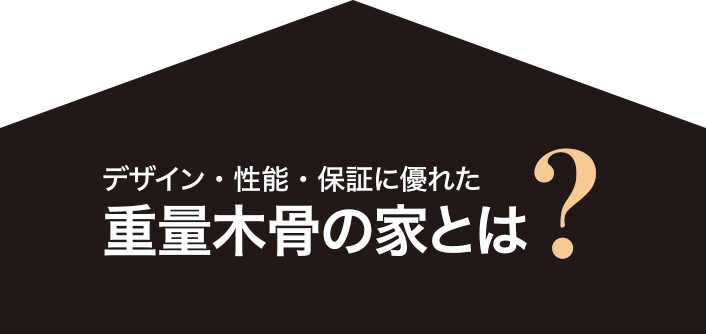











 はこちら
はこちら