注文住宅を建てるときに絶対に知っておきたい「お金の話」

注文住宅を建てるときに絶対に知っておきたい「お金の話」のインデックス
家づくりにおいて大切なお金の話。一見すると「複雑で難しいな」と思いがちですが、とても大事なテーマです。そこを今回はできるだけわかりやすく解説していきます。
1「家づくりにかかる費用とは」
まず、注文住宅を建てる際にかかる全体の費用を知っておきましょう。
1-1「土地取得費&解体費用」
土地の購入から検討されている方には、まず「土地の取得費用」が必要です。土地の購入金額に加えて、不動案会社から仲介で購入する場合は仲介手数料がかかります。通常は3%+6万円+消費税となります。
もし、古屋が建っている場合には解体費用も掛かります。建て替えの方も同様ですね。建物や土地の状況によっても解体費用は変わりますので、事前に不動産屋さんに聞いておいたり、解体業者に見積もりを取っておくとよいでしょう。
1-2「建物建築費以外にかかる費用」
建物については、建物本体の建築工事以外にもいろいろと必要なものがあります。
塀や門扉、駐車場、植栽などの外構工事、カーテンやエアコン、家具など、生活するうえで必要となるものは、最初から想定しておきましょう。
他にも地盤が軟弱な場合には「地盤改良工事」がかかります。また、上下水道の状況によっては「引き込み工事」などがかかる場合もあります。これらは金額的に安くない工事なので、可能な限り早めに調査しておく必要がありますね。
また、「設計費用」や「申請費用」なども建築費以外の費用として実際にはかかるものもあります。住宅会社によって金額も異なりますので、これらもどこまで建築費に含まれているのかを詳しく聞いておいてください。
他にも、「登記費用」や「不動産取得税」「火災保険」なども最初の資金計画に入れおきましょう。
2「資金計画の整理」
全体のイメージがついたら、いよいよ資金計画を作ってきます。ここをしっかり整理して家づくりをスタートすることで、どのくらいの建物が自分たちに可能なのかを自覚することができます。自分たちのライフスタイルやこだわりを実現しながら最適な家を建てる際の金額の基準となります。
結果的に間違いのない自分らしい家ができることになると思います。
一般的に資金計画のベースとなるのは「自己資金」と「住宅ローン」です。
2-1「自己資金について」
「自己資金」は「自分たちの預貯金」と「親からの援助」に分けられます。「預貯金」については自分たちの判断で計画できますが、「親からの援助」については、可能性があるなら事前に相談しておくとよいでしょう。これについては、税務上の控除もありますので、うまく活用したいものです。
ちなみに、平成27年以内の贈与であれば、親からの贈与が最大1,500万円までが非課税となります。(平成28年は最大1,200万円)もし、夫婦それぞれが親から1,500万円ずつ援助を受ければ3,000万円まで非課税となります。
この機会に資産を親から子供へ移動することで、相続税対策にもなります。可能性のある方は是非ご検討ください。
2-2「住宅ローンについて」
次に「住宅ローン」を計画していくことになります。この「住宅ローン」については、ほとんどの方が初めて利用することになると思います。失敗しないためにも、しっかりと勉強してから進めてほしいものです。
最も大事なことは、「どのくらいのお金を借りるかの目安をつける」ことです。漠然として進めていくと、大事な決断をする際に、判断を間違う可能性もあります。間違いのない住宅ローンをお勧めします。
3「住宅ローンの3つの要素」
借りる金額の目安は、以下の3つの要素をベースとします。
- 月々の返済金額
- 借り入れ年数
- 金利
仮でもよいので、いったん全ての設定をしてください。
まず、①の「月々の返済をいくらにするか」。これは、現在の生活を基準に考えることになるでしょう。賃貸住まいの方は、現在支払っている「家賃」+「共益費」+「駐車場」の合計金額が基準となります。それに加えて、「家づくりのために貯金していた金額」など、余裕度を含めてプラスアルファをいくらまで可能かどうかを考慮しながら決めていきます。
次に、②の「何年で返済していくか」を決めます。住宅ローンの場合は、最終返済の年齢が決まっているので、今の年齢から考えて最長35年以内で計画します。
ちなみにフラット35では、返済終了年齢は80歳です。
そして、最後に③の金利となります。現在は低金利時代なので、非常にメリットがありますよね。ただし、金利は「固定金利」と「変動金利」と2種類あり、大きく意味が異なるので注意が必要です。これは後ほど詳しく解説します。
これらの3つの数字から逆算をしていくと、借り入れ想定金額が出てきます。そして、「その金額が借り入れ可能か」という流れになります。
審査に関しては金融機関のそれぞれの基準もあるので、一概に言えませんが、現在の年収や勤続年数、他の借り入れ状況などがベースとなります。ちなみにフラット35では、年収の30%~35%が年間の支払総額の上限となっています。
変動金利の場合は金利上昇リスクがあるので、もう少し厳しいようです。いずれにしても、早めに「事前審査」をしておくと安心ですね。「事前審査」は意外と簡単にできますので、早い段階でやってみることをお勧めします。
4「ケーススタディ」
この考え方で資金計画をした事例をいくつかあげてみます。
例1)
38歳
自己資金500万円
家賃+共益費10万円
駐車場1万円
プラスアルファ1万円
年収600万
月々の支払いを12万円、35年返済とします。
金利を1%とすると、借り入れ可能な金額が4,251万円となり、必要な年収は411万円となりますので、他に借り入れがなければこの計画が一つの基準となります。
家づくりの総予算は500万円+4,251万円=4,751万円となります。
例2)
49歳
自己資金1,000万円
家賃+共益費16万
駐車場1万円
プラスアルファ2万円
年収800万
月々の支払いを19万円、31年返済とします。
金利を1%とすると、借り入れ可能金額は6,075万円となり、必要年収は651万円となります。家づくり総予算は1,000万円+6,075万円=7,075万円となります。
ちなみに、金利が1%上昇すると数字は大きく異なってきます。
金利2%となれば、例1)の場合、4,251万円 → 3,622万円 例2)の場合、6,075万円 → 5,264万円となり、月々返済から逆算する借り入れ可能金額が大きく下がります。
月々の返済は変わらないのに、たった1%金利が上昇しただけで非常に大きな差となることを考えると、現在の低金利の状況が、いかにメリットが大きいかを痛感しますね。
5「変動金利」と「固定金利」
ただし、いくら現在の金利が低いといっても「変動金利」で借りる際には注意が必要です。
最初の借り入れ時点では「変動金利」の方が「固定金利」より低い金利なので、迷うところだと思いますが、長期的なことも考慮して選択してください。
「金利」というものは、経済状況等によって変わっていきます。その時代の金利状況によって返済の金利が変わるものを「変動金利」、世の中の金利状況が変わったとしても自分の返済の金利は変わらないものを「固定金利」ということになります。
「どちらが得か」という視点で考えるか、「どちらが安心か」という視点で考えるかで、その選択は変わります。
借りたときよりもだんだん金利が下がってきたら、「変動金利」の方が得ですし、「固定金利」で損したという話になります。
また、金利が上昇して来たら「固定金利」で良かったという話になりますし、「変動金利」で返済が大変だということにもなりかねません。幸い、しばらくは低金利時代が続いているので、金利上昇リスクを体験した方は少ないと思いますが、これからはどうなるかはわからないのも事実です。
現在の低金利時代に借りるなら「固定金利」でもそれほど大きく損することはないでしょう。「変動金利」で借りる人は、そういう認識を持ったうえで、余裕を持った返済計画を立てることが望まれます。また、これからの社会情勢を見ながら繰り上げ返済なども想定しながら、借りる必要があるではないかと思います。
そういうことを踏まえて考えると、最初に資金計画段階のベースを決める際には、返済金額が変わらない「固定金利」で計画することをお勧めします。その後に、「変動金利」とも比較検討して、どちらにするかを最終決定をするという形です。
「固定金利」の代表格がフラット35です。昔の「住宅金融公庫」といわれていた公的な住宅ローンの制度なので、一度検討してみるとよいと思います。
6「万が一の時のための団体信用生命保険」
他にも知っておいてほしい情報として、生命保険があります。住宅ローンには「団体信用生命保険(団信)」という特殊な保険があるのをご存知でしょうか。
これは、借り入れ名義の方に「万が一」があったときには、残りの住宅ローンの残債がゼロになるという保険です。フラット35では、月々の返済とは別に申し込みますが、民間ローンには金利に含まれているケースが多いようです。
この団信生命保険に入ることを考えれば、現在加入している生命保険を見直してもよいかもしれません。その余分な保険代を月々の返済に充てることも可能です。
7「国のバックアップの住宅ローン減税」

また、住宅ローンを借りる方にとって、国の大きなバックアップとなるのが「住宅ローン減税」です。これは、住宅ローンの残債額に応じて、所得税や住民税(最大年間13万6,500円まで)が還付される制度です。現在は10年にわたって残債額の1%、年間最大50万円(一般住宅40万)、10年間で最大500万円(一般住宅400万)の還付が可能です。
これも一般住宅は最大400万円ですが、長期優良住宅や認定低炭素住宅など品質の高い住宅の場合は最大500万円となることも覚えておいてください。
これらは、あくまでも納めている範囲での還付ですので、現時点でどこまで還付されるかはそれぞれ異なります。サラリーマンの方は年末調整の明細をご覧になって、現在支払っている所得税と住民税を調べてみてください。
8「住宅ローンにかかる諸費用」
最後に住宅ローンを借りるときに必要な諸費用も検討しましょう。
「保証料」や「手数料」がそれに当たります。金額は金融機関によって異なりますので、よく調べておいた方がよいですね。
また、自己資金の少ない方は、土地購入の際や建築費の支払条件に応じて、「つなぎ融資」を使う必要が生じます。一般的に住宅会社が建築を請け負う際には、契約、着工、中間など、3~4階に分けて支払うことがほとんどです。自己資金が足りない場合は、金融機関から借り入れ金額の範囲内で「つなぎ融資」という形で先行して融資をしてもらうことになります。その際には、「金利」だけを経費として支払うことになります。
金融機関によっては、「つなぎ」ではなく、最初に融資を実行してしまって、そこから土地購入費用や建築資金を支払っていく方法もあります。つなぎの金利費用はかかりませんが、早めに支払が始まるというデメリットもあります。
いずれにしても、借り入れを行う際にはどちらになり、費用がどのくらい発生するかを聞いておくとよいと思います。
このように資金計画の全体像をしっかりと把握してから、計画性のある家づくりに取り組んでいただければと思います。自分たちだけではわからない場合には、信頼できる住宅会社に相談することも大事です。信頼できる住宅会社と相談しながら、間違いのない満足できる家づくりを実現してほしいと思います。

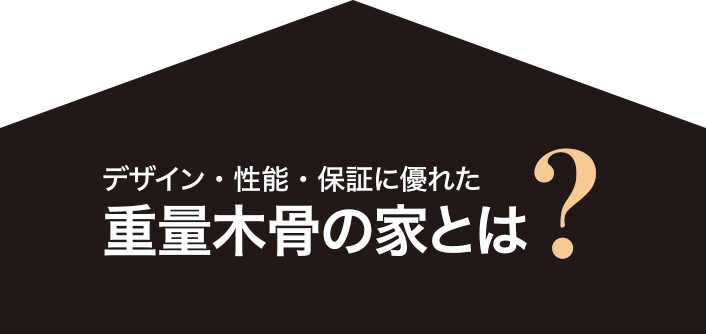









 はこちら
はこちら