二世帯住宅の間取り3パターンのメリット・デメリット、知っておきたい税金のハナシ

二世帯住宅の間取り3パターンのメリット・デメリット、知っておきたい税金のハナシのインデックス
親御さん世帯・お子さん世帯を「共に暮らす場所」でつなぐ二世帯住宅は、お互いの生活を見守れるという大きなメリットがあります。親御さんの体調を気遣ったり、親御さんがお孫さんの育児の手伝いをしたりと、相互に寄り添い合う暮らしを実現してくれます。しかし、親世帯・子世帯それぞれの暮らし方が異なることもありますので、間取りの点で気をつけなければならないこともあります。
二世帯住宅をつくるにあたって、間取りで考えなければならないこと、利用できる補助金など、二世帯住宅にまつわる事柄をご説明します。
1.二世帯住宅間取りには、どんなものがある?メリット・デメリットは?
二世帯住宅は、大まかに以下のような3つの間取りの種類があります。それぞれのメリット・デメリットを知り、家づくりにお役立てください。
1-1.完全同居型の間取り
家族を構成する人たちそれぞれに必要な寝室を設け、それ以外は全て共用するのが「完全同居形」間取りの二世帯住宅です。
親世帯・子世帯内で生活の時間帯に大きな開きがないときには、この完全同居型間取りにすれば交流の時間も増えますので、大家族の醍醐味を味わえる家ができます。誰かがリビングにいて、夜もどこかに明かりがついている生活は、心も豊かに家族の生活を楽しむことができるでしょう。
一方で、生活の時間帯が大きく異なるときや、家事を担う方(親世帯ならお姑さん、子世帯ならお嫁さん)との関係性によっては、気を遣い合わなければならないちょっと窮屈な家になるかもしれません。
1-2.部分共用型の間取り
玄関や浴室などの設備の一部を共用しながらも、親世帯・子世帯が生活するゾーンを分けるのが「部分共用型」間取りの二世帯住宅です。
親世帯と子世帯の生活時間帯が異なる場合や、適度にプライバシーを保ちたいときにこの部分共用型の間取りを選ぶと良いでしょう。共用する部分が増えれば、その分、建築にかかるコストを抑えることができます。
2階建てなら1階に親世帯を、2階に子世帯を配置する間取りが、平屋建てならキッチンや浴室を中心として親世帯と子世帯を左右に振り分ける間取りが考えられます。
もしも生活時間帯が異なるという理由で部分共用型の間取りにするときは、浴室を使用する際の水音、室内を歩くときの足音が相互世帯ゾーンに響かないよう配慮する必要があります。
1-3.完全分離型の間取り
「完全分離型」は、その名の通り、全く別の世帯として暮らす間取りです。同じマンションの隣同士で生活をするイメージを思い描いていただければよいでしょう。暮らしの全てが完全に分かれますので、すぐそばにいながらも干渉しあわない、いわゆる「スープの冷めない距離」の暮らしが実現できます。
親世帯・子世帯相互に意識して関わりを持たなければその暮らしぶりがわからないことと、建設のコストがほぼ2軒分かかることがデメリットといえます。
2階建てならば家の内側にも階段を設けて行き来できる場所をつくること、平屋建てならば窓越しにでも気配を感じ取れる部屋の配置の工夫を凝らせば、相互の暮らしを干渉せずとも、見守りができる家になります。
→「完全分離型二世帯住宅のメリットやデメリットを徹底解説!事前に知るべきポイントはこれ!」
2.二世帯住宅を建てるときに使える補助金はある?その条件は?
国が指し示す家族のあり方は、親と子が支えあうというスタイルです。在宅介護を行わなければならない家庭も増えていますし、同時に子育てをしている親が子どもを預ける場所を確保できない現状もあります。
親の見守りと子育てを両立しなければならない状態を「ダブルケア」と呼び、「就業構造基本調査」・「国民生活基盤調査」を基にしてダブルケアをしている人を推計したところ、全国で25万3千人いるとの結果が出ました(※1)。
これらの問題を解消・低減する家族像へ近づくための一環として、二世帯住宅を建てる際にも補助金が準備されています。
2-1. 地域型住宅グリーン化事業
環境負荷を低減するために木造の住宅は有効です。これを推進するため、地域の工務店などで木造の家を建てる際に利用できる補助金が「地域型住宅グリーン化事業」です(※2)。この補助金を受けるための条件の一つに
・子育てを家族で支え合える三世代同居など複数世帯の同居しやすい環境づくり
が挙げられています。
ただし、それぞれが独立した2戸は対象外となりますので、上記の「完全分離型」は注意が必要です。
その他に、家の性能も
・長寿命型―長期優良住宅(補助対象となる経費の1割以内、100万円を上限とする)
・高度省エネ型―認定低炭素住宅(同上)
・高度省エネ型―性能向上計画認定住宅(同上)
・高度省エネ型―ゼロ・エネルギー住宅(補助対象となる経費の2分の1以内、165万円を上限とする)
・優良建築物型―認定低炭素建築物等一定の良質な建築物(1平方メートルあたり1万円、1,000万円を上限とする)
の5分野がありますので、この事業に参加し、登録しているグループ(工務店)を探して相談してください(※3)。
2-2.すまい給付金
「すまい給付金」は、消費税引き上げに伴った負担増をカバーするためにつくられた制度で、平成31年6月まで実施されます。
・自分の家を建てること
・収入額が一定以下であること(各種条件あり)
・床面積が50平方メートル以上であること
を満たしながら、
・新築か、中古住宅か
・住宅ローンを利用しているか、していないか
といった条件によっても給付要件が変わってきます。
給付は、原則として住宅の引渡しが完了してから1年以内です。申請は住宅を取得した本人ですが、工務店などの事業者が代行することも認められています。自分が建てようとしている家が対象になるのか、対象になるのであればいくら位の給付金が受けられるのかの参考にできるよう、専用のサイトが設けられています(※4)。
3.二世帯住宅における税金対策や贈与税は?
住宅を相続した場合には相続税がかかります。また、住宅を購入する際に親から資金を出してもらったときには贈与税がかかります。これらもまた、二世帯住宅を建てることでとても有利に運びます。
3-1.税金対策としての二世帯住宅
家を相続した方が、被相続人(財産を遺して死亡した人)と同居していた親族だった場合、相続税の申告期限までに住まいや土地の所有を続けていたことを条件に土地の評価額を8割減額する制度が存在します。これを「小規模宅地等の特例」(※5)と呼びますが、先に挙げたとおり、同居していた事実があり、なおかつ続けて住まい続けていることが求められます。
「親の面倒を見なければならないから、実家のそばで家を建てようか」「実家も古くなったからリフォームしなければ」といった場合は、思い切って二世帯住宅を建て、一緒に住まうことで安心を得られますし、同時に後の相続税を安く抑えることができます。
3-2.二世帯住宅に関連した贈与税はどうなる?
親に何がしかの金品を贈与された場合、贈与税がかかります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産から110万円を差し引いた額に税率をかけた額が贈与税となります。
しかし、住宅資金としてお金を贈与された年の合計所得金額が2,000万円以下であることなどいくつかの条件を満たしたとき、非課税の特例の対象となります(※6)。
・平成29年9月まで―良質な住宅用家屋ならば1,200万円まで、以外は700万円まで
・平成29年10月~平成30年9月まで―良質な住宅用家屋ならば1,000万円まで、以外は500万円まで
・平成30年10月~平成31年6月まで―良質な住宅用家屋ならば800万円まで、以外は300万円
上記が、非課税の対象です。ここでいう「良質な住宅用家屋」とは、省エネ性・耐震性・バリアフリーなど、国の示す条件を満たす家を指します(※7)。
3-3.税制面で何が有利なのかは、税金に明るい担当者に相談を
二世帯住宅には、ケースに応じ、相続税や贈与税がかかることになります。どのようにするのがベストなのかは、種々の条件により異なりますので、工務店やハウスメーカーの相談窓口で相談してください。一番避けたいのは、相続・贈与される関係者間の揉め事です。充分な配慮をしなければなりません。
【実例紹介】二世帯住宅の間取りの参考に
二世帯住宅を建てるときに気をつけなければならないことは、間取りとお金の問題ですが、これは家族構成や暮らし方が最も大きなポイントです。まずは間取りなど家のつくり方を知るところから始めませんか。
家族の暮らし方に寄り添う機能的で美しい二世帯住宅をご紹介します。それぞれに独特の工夫を凝らしていますので、きっとあなたの望む二世帯住宅の間取りのヒントがあるはずです。

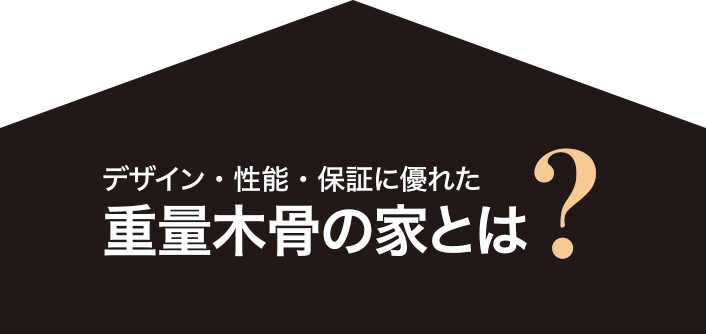









 はこちら
はこちら