高気密高断熱の家で健康被害を最小限にする方法

高気密高断熱の家で健康被害を最小限にする方法のインデックス
あなたにとって、家とはどのような場所でしょうか。どんな暮らしを思い描いていますか。家のスタイルと同様、大切な要素に「家の性能」があります。家は、どんなに短くても就寝+アルファの時間、長ければ一日中いる場所です。緊張感をほぐしリラックスできる場所、健康を守るため安全安心の側面から「家の性能」にも注目してください。家と健康の関係性、あなたはどのように考えていますか。家ではどんな問題が起きてきたのでしょうか。それを踏まえて身も心も自由になる良い家を作るためには、どこに気をつければよいのかをご説明いたします。
1.【高齢化にまつわる家の問題】死につながるヒートショック
家と健康の関係性で注目されているのがヒートショックです。ヒートショックと関連があるだろうとされる浴室での溺死は、1年の間に2万人に迫る勢いで増加中です。消費者庁が2016年1月20日に発表した「冬場に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!」という資料では、冬場の入浴で一番に気をつけるべきこととして「入浴前に脱衣所や浴室を暖めること」を挙げています。これまでの家は、陽当りの悪い敷地の北側に配置されることの多い浴室やトイレがとても寒いものでした。暖かい部屋からの移動、そして衣服を脱ぐことで起こる身体表面の温度の急激な低下、血圧の上昇。さらに、温かい湯に浸かる事で血管が拡張し、血圧が低下します。このような血圧の大きな変動を避ける対策を行っていれば、ヒートショックを抑制でき、溺死のうちの何割かは防げたものかもしれません。
健康な若い方であっても、暖房の効いた部屋からお風呂場やトイレに移動するだけでゾクゾクとした寒気を経験し風邪をひいてしまうことがあります。高齢とはいえない年齢だとしても、早朝の血圧が高い「早朝高血圧」の傾向を持っている方が冬季早朝の寒いトイレで体調を崩すことがあります。夏場であっても安心はできず、エアコンの効いた部屋とそうでない部屋を行き来することで引き起こされる夏型ヒートショックの事例もあるのです。
人間の体が、部屋移動による急激な温度変化に耐え得る幅は5~7度といわれています。家の中が均一の温度を保てるような工夫が大切です。
2.【密集化にまつわる家の問題】騒音が睡眠を妨げ様々な症状を引き起こす
家は最もリラックスできる場であるはずなのに、周囲から聞こえてくる音によって眠れない、くつろげないという話を聞くことがあります。例えば高速道路や幹線道路、線路のそばにある家、そして住宅が集まったエリアで音の問題が多く発生します。
騒音は睡眠を妨害するだけでなく、リラックスすべきときにリラックスできないことにより日中にも血圧の上昇、心臓疾患、集中力の低下を招くことがあるとされています。身も心も緊張したままの家は、よい家とはいいづらいもの。単なる音が原因であっても、一度気になり始めたらそこから身と心が蝕まれはじめます。会話・音楽・足音に至るまでが騒音となり、心理的なストレスが増していきます。
隣家同士の生活サイクルの違いも問題を大きくします。寝室の窓からほんの数十センチ向こうに隣家のトイレや浴室があるばかりに、眠りを破られることもよく聞く話です。このような問題はお互い様の側面がありますので、「音を出さない・音を入れない」ことが相互の気遣いとして重要です。
音について追加で考えたいことがあります。子どもの声です。育ち盛りの子どもさんが遊ぶときに、あまりに神経質に「静かにしなさい」とはいいたくないのが親心というものです。マナーやルールを逸しない限りは、気持ちまで萎縮させるような叱り方はしたくありません。子どもをのびのびと遊ばせることのできる「音を漏らさない家」は、子育て中の親御さんにとってのどから手が出るほど欲しい環境ではないでしょうか。音にも配慮した家が重要であるのはこういった面もあるのです。
3.【機能不足にまつわる家の問題】結露が引き起こす様々な病気
家と健康の関連性で注目されているものの中に結露があります。結露そのものは健康に直接被害を与えるものではありませんが、次のような病気・症状の原因となります。
3-1.カビから肺炎・喘息・鼻炎が発生することも
カビはヒトの暮らすところのどこにでもいますが、湿度が60%を越えると活発に活動しはじめ、80%では喜んで増殖します。特にアスペルギルスやトリコスポロン、アルテルナリアと呼ばれるカビは厄介です。ちょっとした夏風邪と思わせる症状でありながら、かなり深刻な肺炎やアレルギーを引き起こしていることがあるのです。
咳が続くことを自覚していても「熱もほとんどないから」と放置していた人が、入院することになったという例を聞くことがあります。オフシーズンにエアコン内に発生したカビを、エアコンを使用する夏に部屋にばら撒いてしまうことによって起きるこの病気は、結露から起きる病気の代表例といってもいいでしょう。
そのほかにも、結露しやすい窓にかけるカーテンにカビが発生していることもあります。天気の良い日は窓を開けますが、このとき風に揺れたカーテンからカビの胞子が放出されます。エアコンもカーテンも、なかなか目が行き届かないだけに体調変化を経験してから気がついた、ということも珍しくありません。
3-2.ダニでアレルギーや肺炎が重症化?
ダニも湿気が大好きで湿度の上がる季節に大発生します。このダニの死骸やフンがアレルギーや肺炎の原因となります。最近では開封済みのホットケーキミックスの中で大繁殖したコナヒョウダニに気づかず調理し、食べた方がアレルギー反応を起こして病院へ運ばれた「パンケーキ症候群」もニュースになりました。
ダニは室内のホコリなどに住み着きます。理屈の上ではホコリをシャットアウトするとダニの数も大幅に減るのですが、掃除機をかけたり人が歩いたりするだけで空中に舞い上がるホコリは、完全になくすことは不可能です。ダニの抑制に霧タイプの薬剤を使うことがありますが、この薬剤もまたアレルギー元となることがありまさしく“痛し痒し”です。
ダニを活動させない・増殖させないために湿気をコントロールするのが一番手っ取り早くはあるのですが、結露の多い家では湿度の管理はとても難しいものです。
3-3.家の中でも花粉症の症状がつらい…
花粉症アレルギーの方にとって、春先から初夏にかけてはとても辛いものです。花粉症は春先のスギ・ヒノキだけでなく、マツやイネ、ブタクサ、セイタカアワダチソウといった他の季節の花粉が原因のこともあります。中にはほぼ一年中何らかの花粉に反応してしまうという方もいらっしゃいますが、本当に深刻なお話です。外出先から花粉を持ち帰らないよう心がけ、室内でも空気清浄機を運転していてもずっとくしゃみや咳、微熱が出る…これでは休まる場所がありません。隙間の多い家では、アレルギーのもととなる花粉そのものを遮断することが難しいことは事実です。目に見えない花粉と戦うためには、家にそれを持ち込まない努力と、入り込む隙間を極限までふさぐことが大切です。
4.身体と心の健康には、「高気密」「高断熱」のふたつが有効
上記の問題はすべて「家と健康の関係」。家は雨露をしのぎ、眠れる場所であればいいという訳ではありません。健康を損なわない、健康状態を向上させる家が望ましいです。
・家全体がほぼ均一の温度を保てるように
・音を外にもらさない・外の音を室内に入れないように
・結露させないように
を実現するためには、「高気密」「高断熱」のふたつのポイントを押さえなければなりません。
健康的な暮らし、健康を増進する生活を心置きなく楽しむために、高気密・高断熱は今や欠かせない性能です。温かく(もしくは涼しく)静かでダニやカビが発生しづらいクリーンな家は、小さなお子さまからご高齢の方にまでやさしい家です。
5.「高気密」「高断熱」の家とはどんな家?
壁と窓枠、壁のつなぎ目部分、配管周囲など、質の違う部材が交わる部分はなじみにくいものです。このような部分で生じがちな隙間を極限までなくすのが高気密の家です。従来の日本家屋は、土壁の縁がもろくなり隙間が生じていましたが、それを防止するため木の壁やモルタルの壁を取り入れるようになった歴史があります。雨や風を遮断したいという願いが家を進化させてきたのです。
温めても温めても寒さが忍び寄る家をどうにかしたいと、断熱材を入れる家も増え、今や当然のこととなっています。熱の出入りが生じる屋根や壁、床などに断熱材を入れて熱のロスを抑えた高断熱の家は、寒さ・暑さから家族を守ってくれます。家全体で断熱を図れば、屋内の温度が外気に大きく影響されることがありませんし、部屋ごとに室温が大きく異なることも減るのです。つまり、ヒートショックからくる健康上のトラブルを防げる可能性が高まるのです。
高気密・高断熱の家は、上記1~3の項で触れた心身の健康の問題を軽くしてくれます。この点を注意して家づくりに取り組むと、快適に生活ができる家になるのです。
6.実現したいライフスタイルに「性能」の視点も取り入れて
家を建てる―好みのデザインを思い巡らし、そこでしてみたいことをイメージするだけでも新しい生活への期待が高まります。広いリビングで家族や友人と団らん、できればウッドデッキを作って夏にはバーベキューを、収納を多く準備して家具を置かないさっぱりとした暮らし方を…。望むデザインやライフスタイルとともに、家の性能もプラスしてご検討ください。年齢や体質を問わず誰もが快適さを感じることのできる「高機密」「高断熱」という性能は、心身を癒すために重要な視点のひとつです。

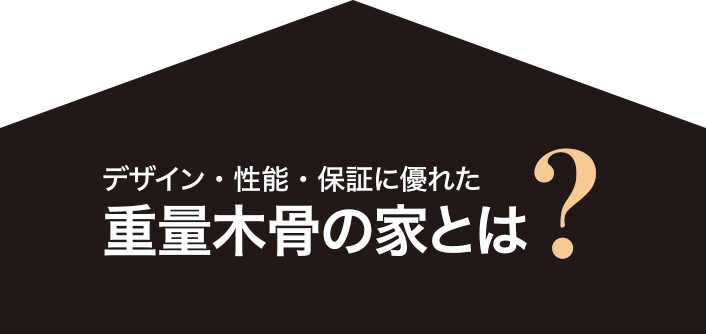






 はこちら
はこちら