旗竿地に住宅を建てるメリットとは? デメリットや注意点もしっかり解説します!

旗竿地に住宅を建てるメリットとは? デメリットや注意点もしっかり解説します!のインデックス
家を建てるための土地をお探しであれば、目にする機会もある「旗竿地」という言葉。一般的にはあまり歓迎されない条件の土地ですが、実はメリットはたくさんあります。もちろん、デメリットもありますが、デザインや工夫をすることで、デメリットではなくなる場合もあります。旗竿地について詳しく知ることで、建築地としての候補に入ってくるかもしれませんよ。また、最後にご紹介する素敵な実例を見ることで、旗竿地という土地が持つイメージが変わるかもしれません。
旗竿地とは

旗竿地とは、旗とそれがつく竿の形状をした土地のことです。日本の法律で、道路に2m以上接してない土地には、建物を新築できないというものがあります。その結果、大きな土地を前面と背面に分割した時に、その奥の土地が道路に接するためには、最低2mの細長い通路のような土地が必要になります。その通路と奥に位置する土地が、旗竿地と呼ばれます。旗竿地は、前面の土地に建物が建っている場合、日照や通風を奥まで取り込む工夫が必要です。
旗竿地のメリット

旗竿地はその形状だけを見ると、デメリットしかないようですが、見方を変えればメリットといえる点があります。以下の4つのメリットについて魅力的だと感じるようであれば、旗竿地を建築敷地として、候補に入れみてはいかがでしょうか。
土地の値段が相場より安い
不動産業界では整形の土地の方が、建物も建てやすく望ましいとされているため、旗竿地のような不整形の土地は、同じ地域の整形地に比べて、価格が低く設定されることが一般的です。土地が予算より安く手に入れば、建物や外構に予算の浮いた分を回すことも可能です。
静かな住環境が実現しやすい
旗竿地は、道路が敷地の通路に当たる部分にしか接していないため、敷地としては奥まった配置になります。その為、交通量が多少ある道路だとしても騒音からも遠ざかることから、静かな住環境が手に入りやすいでしょう。また、同じく道路側に直接建物が接していないことから、道路面からの視線は届きにくく、近隣への配慮をすれば、プライバシーの面からも落ち着いて暮らしやすいと言えるでしょう。また子供が小さいうちに、急に道路に飛び出すという可能性も少なく安心ですね。
路地の部分を家づくりに活かせる
通常の家づくりでは、駐車スペースを確保してから家づくりを考えることになりますが、旗竿地の場合は、既に車が通る幅が確保された通路の部分があります。通路部分を駐車スペースとすれば、奥の整形の土地に家を計画することができます。また、旗竿地の竿部分は外構にこだわったアプローチにすることも可能ですし、あえて建物を計画して個性的な建築とすることもできます。
整形地と比べると、延べ床面積の広い家を建てられる
建築基準法上、建物を建てる際には敷地面積に比例して、建てられる建築面積と延べ面積が決まっています。旗竿地の場合は、竿部分の土地も含んだ敷地面積となるので、その分建てられる建築面積と延べ面積も大きくなるということです。旗竿地の旗部分の敷地と同じ面積の整形地を比較すると、より大きな建物を建てられるので、各部屋の空間も余裕をもってデザイン出来ますね。
旗竿地のデメリットと解決策

次に旗竿地のデメリットについて見てみましょう。ただ、デメリットと言っても工夫次第でデメリットと感じなくなることもあります。また、メリットと比べてみて、メリットの方が多いと感じれば十分に検討する余地はあると言えるでしょう。
外構工事のコストが高くなることも
旗竿地は敷地に竿部分の長さがあるので、敷地全体に塀を回すとなると塀が長くなることは想定できます。その分は当然コストアップにつながりますが、デザインによってオープンな作りにすることもできますので、デザインを重視される方にとっては、そこまでのデメリットに感じられないでしょう。また、建築工事の際に、部材の運び込みや重機の進入などが制限されて、手作業部分が増えると、コストアップにつながる可能性もあります。事前に建築会社に確認することが必要ですね。
風通しや採光の確保に工夫が必要
旗竿地は奥まった位置にあるので、周辺を建物に囲まれる可能性が高くなります。そうすると、採光や通風の面では不利になってしまうという事も考えられます。ただ、2階以上をリビングにしたり、中庭型のコートハウスにするなど、デザイン次第で解決できることもあります。どのような設計ができるのか事前に良く打ち合わせをしましょう。静かな環境がメリットでもありますので、デザインの力でデメリットをメリットに変えられれば旗竿地の魅力も増しますね。
お隣との距離が近くなる
旗竿地は全体としての敷地面積が大きくなる分、建築面積、延べ面積ともに大きく出来るというメリットがありますが、その分、敷地目一杯に建物が建つ可能性があります。これは、隣家との距離が近くなるということですので、音や匂い、視線の方向などに気を付ける必要があるでしょう。ただ、この問題に対しても窓の位置を工夫したり、中庭方式にするなど、外に閉じたデザインにすることで解決できることもあります。
旗竿地に家を建てるときの注意点

旗竿地に家を建てるためには、通常の整形地に比べて、事前に調べておいた方がいいことがいくつかあります。旗竿地での家の建築を考える際には、建て始めてから、しまった! ということにならないよう、事前によく確認しておきましょう。
路地部分の幅を確認する
旗竿地には、竿部分の路地があります。この路地の幅は、最低2mは必要であると法律上決まっているので、2m以上の道路に接していない土地には新築建物は建てられません。古い建物が建っていて、改築しかできないということもありますので注意しましょう。
また、その路地部分の幅によって、できることが変わってきます。例えば、法律ギリギリの2mしかない場合は、駐車スペース+人が通れるアプローチという計画は、非常に厳しくなるでしょう。場合によっては駐車場を作れないという可能性もありますので、事前にチェックしましょう。
インフラの整備は問題ないか
新築用の分譲地として販売されている土地の場合、水道や電気、ガス等があらかじめ敷設されていない場合もあります。新たに分譲された土地の購入を検討している場合は、事前に確認が必要です。もし敷設されていない場合でも、旗竿地は通常売れ残ることが多いため、購入者側は交渉しやすい可能性もあります。また、建物が建っていた場合でも、電線が隣地の上空に越境している場合などもあるので、調査しておくといいでしょう。
工事車両が入れるか
旗竿地は、実際に建物を建てる敷地が前面道路から離れているため、工事の為に必要なクレーンや重機などは前面道路に駐車できず、敷地の中に入れる必要があります。その際に、路地部分が、工事車両の通行できる幅を確保できないと、車両を入れることが出来ず、材料を手運びしたり、重機の代わりに職人の手作業が必要になる場合もあります。
そうなると当然のことながら、費用は高くなりますし、工期も長引きます。土地が割安で手に入る分、工事費に多少の余裕は出てきますが、全体の予算を考えて土地を選ぶかどうかを考えましょう。
旗竿地に建てた注文住宅の実例7選
ここからは旗竿地に建てられた実例をご紹介します。各実例ともに旗竿地ならではの工夫があったり、旗竿地とは思えない開放感があったりと、参考にしたいものばかりです。じっくりと楽しみながらそれぞれの良さを探して見てみてください。
四季を感じられる庭木の植えられた住まい

旗竿地に建つこちらの家のアプローチは、手前に配置された駐車スペースから、平板を用いた飛び石で玄関へと導かれます。飛び石の配置は敢えて屈曲させることで、視線を逸らす役割を持たせています。また、周囲を住宅に囲まれた条件であることから、外側には閉じた、中庭に向かって開放感のあるつくりとしています。リビングとダイニングの両方からアクセスできる広いウッドデッキは、アウトドアリビングとして大活躍です。
スキップフロアと2階LDKのある旗竿地の家

旗竿地の中でも、さらに変形タイプのT字型の土地に建つこちらの事例は、隣地に大型マンションが建っているという難しい環境。明るく開放感のある暮らしを確保するために、2階にリビングを計画しました。リビングの外にはバルコニーと、さらにバルコニーから続くデッキテラスもあります。これだけ広い外部スペースがあれば、明るさはもちろん、開放感もたっぷりですね。テラスの下は駐車スペースとなっており雨の日も濡れずに安心です。
旗竿地でも開放的な吹き抜けのリビング

玄関扉を開けると、中庭タイプの外土間へ通じた開口部からの光が、玄関全体に明るさを届けています。この外土間は、隣家の路地部分に面していますが、目隠しを設置し、視線が気にならないように工夫されています。また1階に計画されたLDKは、大きな吹き抜けがあり、その吹き抜けの上部に設置された開口部からの光が降り注いでいます。また、外土間にも履き出し窓が設置されているので、そこからの光も届き、旗竿地の1階とは思えない明るい空間に仕上がっています。
旗竿地を活かしたコの字プランの家

旗竿地の路地部分を存分に活かした事例です。駐車スペースにも緑が沢山施され、その脇には飛び石を配置した芝生のアプローチがあります。そのアプローチを進んでいくと、木製のパーゴラが駐輪スペースと玄関までのアプローチの屋根として外構を彩っています。建物をコの字型に配置することで、中庭タイプのウッドデッキも設けることが出来ます。それにより空間も広がり、明るさと開放感をたっぷり味わえます。
庭を囲み、内側に開いた家

こちらの事例は、旗竿地でも周囲の視線を気にせずに暮らせるように、ロの字型のコートハウスとして計画されました。玄関までは、外壁につけられた和モダンの門扉を開けて、中庭を眺めながらアプローチを通ってたどり着きます。どの部屋からも中庭が眺められて、外からは想像できないほど開放的な空間が広がっています。南側の和室部分を敢えて平屋にしたことで、太陽光を中庭に届きやすくしています。
遊び心のある、旗竿地に建つ開放的な住まい

こちらの事例では、光を高い位置から取り込むことで、旗竿地でも明るい空間を実現しています。また、基本的にはスタイリッシュでクールなイメージの内装ですが、ところどころに色で遊びを入れることで、カラフルで楽しい空間となっています。暗いイメージになりがちな地下にある書庫を、敢えて明るいグリーンで彩っているのも遊び心いっぱいですね。また玄関ホールにはボルダリングが出来る設備が整えられており、この場所もカラフルな仕上げで明るい雰囲気です。
庭に対して開くL字型プランの家

こちらの事例は、旗竿地でありながら隣地は親戚が住む家が建っているということで、周囲からの視線をそれほど気にせずに済むという好条件の土地です。また、敷地面積が広く明るさを存分に取り込めるので、家の中で太陽の光が反射し過ぎないように、壁紙を薄いグレーで仕上げています。元々その土地に植わっていたという庭木や花の眺めを家の中から楽しめるように、建物をL型に配置しています。
まとめ
今回は、旗竿地に建つ家について見てみました。旗竿地には、一般的には敬遠されがちな条件もあります。けれども、実例を見て頂くと分かるように、これが旗竿地に建つ家なのかというくらいに明るい大空間を持つ家を建てることもできます。敷地が持つデメリットになり得る条件は、建築設計の工夫により、いくらでもメリットへ変えられると言えるのではないでしょうか。後は、旗竿地であることで、余計な支出がないかどうかをチェックして、トータルバランスを見ながらじっくり検討してくださいね。

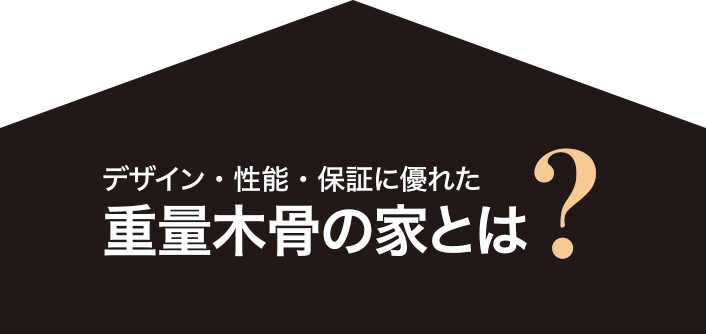






 はこちら
はこちら