玄関の防犯と実用性を重視したい人必見!実例を交えたポイント解説

玄関の防犯と実用性を重視したい人必見!実例を交えたポイント解説のインデックス
玄関はその家を印象付ける大事な「顔」です。家族が仕事や学校へ出かけ、帰ってくる場所ですし、お客様を迎える場所でもあります。家の中と外をつなぐ場所であるだけに、防犯面からも玄関周りを考える必要があります。玄関を安心な場所とするために導入を検討したい設備や、快適に使用できるドア・床材についてご説明します。
1.玄関は家の中と外をダイレクトにつなぐ場所、防犯面での工夫を
玄関は家族が外の世界とのつながりを感じる場所です。それと同時に、外部から人や視線が入り込みやすい場所でもあります。防犯面での工夫がとても大切です。
1-1. センサーライトを設置し、使いやすく入りづらい玄関に
センサーライトとは、人やものの動きにセンサーが反応し自動でオン・オフする照明器具です(センサーの仕組みはメーカーや機種により異なります)。夜遅くに帰宅したとき、家人がドアキーを捜し、鍵を開ける際にもとても便利なものです。
しかし、その効果は防犯面でも発揮されます。ライトがつけば、住まい手に「だれかが近づいた」と知らせてくれますし、侵入しようとした者へは「気づかれたか」と感じさせる心理的効果があります。
侵入者の行動を直接的に押しとどめる力はないものの、防犯面で一番大切とされる「この家は防犯にとても気を使っている、入りにくい」と認識させる効果があります。
1-2.防犯砂利で敷地に人が立ち入る音を感知
防犯砂利とは、踏み締めたときに大きな音を立てるよう工夫されたものです。より高い効果を持たせた製品ならば、その音量は約80デシベルです。80デシベルといえば、救急車のサイレンをすぐそばで聞くほどの音ですので、室内で、よほど大きな音で映画や音楽を流していなければすぐに気づくほどです(※2)。
しかしながら、人が常に出入りするアプローチ部分にまで敷いてしまえば、住まい手側が防犯砂利の音に慣れてしまいます。侵入者が好む死角になりがちな部分(アプローチの脇や犬走りなど)を中心に敷くとよいでしょう。
1-3.液晶モニター付きインターホンで、訪問者をチェックできるように
来訪者の存在を知らせるインターホンも、液晶モニター付きにしましょう。誰が玄関にいるのかを出迎える前に知ることができますので、心構えができます。特にお子さんのいるご家庭には必須です。日頃から知らない人にはドアを開けないよう教えてはいても、玄関のドア越しでの対応では判断に迷うこともあるからです。安全なリビングで、来訪者が誰なのかがわかることが防犯につながります。
2.ガレージやカーポートも要注意
ガレージやカーポートも住まい手の出入りと言う点では玄関の延長線上にあるもので、防犯面での配慮が必要です。車がなければ、「家には誰もいない」と思われてしまうこともあるからです。

2-1.ガレージにはシャッターをつける
ガレージは、車だけでなくスタッドレスタイヤや工具などを収納する場として使います。また壁に囲まれているので、誰かが侵入しても気づきにくいものです。盗難や不審者の侵入を防ぐために、できればシャッターをつけることをおすすめします。
2-2.カーポートには、二重・三重の防犯対策を
カーポートも、車のあり・なしで「狙いやすい家かどうか」が判断される場所です。「不在時でも防犯対策をしている」ことを知らせるよう、センサーライトや防犯カメラを設置するとよいでしょう。
また、カーポートと2階のバルコニーやベランダが近ければ、家への侵入ルートを作ってしまうこともあります。敷地の問題で近くに設置せざるを得ないときは、2階から照らす位置にセンサーライトをつけたり、2階バルコニーの手すりを隠れ場所のないオープンなタイプにするといった工夫をしましょう。
3.実用と安全面を検討して玄関の位置を決める
玄関は、その家を印象付ける部分であると同時に、様々なものの出入り口でもあります。以下のような点に気をつけて玄関の位置を決めましょう。
3-1.方角はその土地の条件や地域の気候風土を考慮して決める
玄関の位置は、敷地の形状や隣家との関係、時には風水の考え方を取り入れて決めるものです。しかしながら、雪が多く降るエリアでは、実用や安全の観点から東南に玄関を設置することを避けることがあります。屋根に積もった雪が北西から吹いてくる風に押し出され、東南方向の屋根から垂れ下がり、巻きだれや氷柱ができて危険だからです。豪雪地帯でなくても、風通しや日当たりといった気候条件を考えなければなりません。
玄関のすぐ前が交通量の多い幹線道路という危険な状態を避けるため、もしくは通りから生活感をうかがわせないよう玄関の位置をあえて通りから離すこともあります。
4.玄関のドアはどう選べばよいか
玄関のドアも、家の雰囲気や使い勝手に大きな影響を与えます。ドアの種類それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
4-1.内開きドアは防犯面で大きなメリットが
内開きとは、ドアが玄関側に開く(室内から見れば手前に引く)タイプのドアです。内開きは玄関で靴を脱ぐ日本の家では多少の不便を感じますが、防犯面ではとても有利です。たとえば不審な人が入ってこようとしたとき、全体重をかけてドアに体当たりをすれば閉めることができますし、水害に遭ってしまったとき水圧を利用して開けやすいドアといえます。
また、蝶番(ちょうつがい)やかんぬきなど、セキュリティ上見せたくないものが見えづらいという点も大きなメリットです。
4-2.外開きドアは「日本の暮らし」にマッチ
玄関で靴を脱ぐ習慣のある日本の家屋では外開きドアに軍配があがるかもしれません。玄関のたたき(靴で出入りできる部分)をさほど広く取れないときは、「外開きしか選択肢がない」と考えてしまうかもしれませんし、実際外開きの家が多いのも現実です。
4-3.引き戸は「安全」が最大のメリット
どのような方でも暮らしやすい「バリアフリー」の考え方が広まっている中で、引き戸も改めて見直されてきています。玄関ポーチとたたきをフラットにした上でドアを引き戸にすれば、車椅子もベビーカーも容易に出入りすることができます。
また、強風にあおられてドアが閉まることもありませんので、小さなお子様が指を挟むといった事故を大幅に減らすことができます。
しかしながら、バリアフリー仕様の吊り下げ型引き戸は、内開き・外開きの「開き戸」と比較してコストが高くなる傾向にあること、戸の開閉のためのスペースが横に広く必要になることがデメリットです。
5.長く住む家だからこそ「玄関を作る時に気をつけたいこと」
朝、仕事や学校にでかけ、夜には我が家へ帰ってきたと実感できる場所である玄関は、家族を外の世界と結んでくれるとても大切なものです。安心して長く住まうために、家の間取りや内装のイメージと同じくらい、考えなければなりません。
5-1.段差のないバリアフリーを意識すること
バリアフリーといえば、障がい者が使いやすいつくりをイメージしがちですが、生涯のうちに段差のない玄関に助けられることは案外あるものです。たとえば子どもが小さいうちはベビーカーを使います。ケガをしたとき、腰を痛めたときに一時的に松葉杖や車いすを使用することもあるでしょう。妊婦さんがゴミ出しや買い物荷物を運び入れるとき段差が怖いと感じることもあるはずです。
段差をなくし、車いすが通過できる幅を持たせておけば、家族が安心して暮らせますし、ご高齢の親御さん・ご親戚が遊びに来たときも不便がありません。
5-2.雨天でも慌てない工夫を
雨の日に出かけるとき、傘を開くのはドアを出てからです。帰宅したとき、傘やお子さんのレインコートについた雨粒を払い落とすのも玄関ドア前でしょう。軒をつけてください。既に降り始めた雨に影響されずに、雨具の準備ができます。
外開きドアにする場合は、ドア開閉時に必要なスペースに加え、傘の開閉動作がスムーズに行える広さを確保してください。
床材にも、玄関ならではの配慮が必要です。雨が降っても滑らないものにしましょう。出かける前・帰宅したとき、降り込んでくる雨や雨具から落ちた水滴で滑り、けがをしてしまっては大変です。
【玄関の施工例紹介】
玄関は、デザインだけでなく実用性や安全を加味し、充分な検討をしなければならない部分です。日常生活を快適に保たなければなりませんし、お客様を迎え入れるときも気兼ねなく出入りして欲しいものです。しかしながら、「招かれざる客」への対応方法も考えておかなければなりません。
ドアの種類、軒を作ること、滑りにくい床材に加え、防犯対策としてセンサーライトや液晶モニター付きインターホン、玄関そばのガレージやカーポートが“入り口”にならない工夫をします。
玄関周りが特徴的な重量木骨の家をご紹介します。「なぜこのような形にしたのか」がわかれば、玄関がどれほど大切な部分なのかをより明確にご理解いただけます。

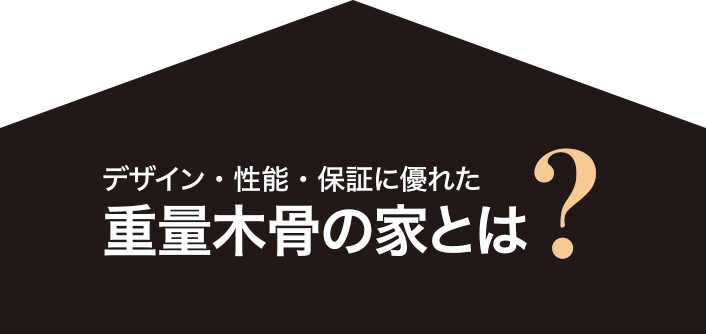










 はこちら
はこちら