セントラルヒーティングで安心安全な温かい家へ!メリットや導入時の注意点を解説

セントラルヒーティングで安心安全な温かい家へ!メリットや導入時の注意点を解説のインデックス
セントラルヒーティングという言葉自体は知っているけど、どういう仕組み? と聞かれると正確に応えられる方は少ないのではないでしょうか。今回はセントラルヒーティングという暖房の仕組みについて、メリットデメリットなども含めて掘り下げて調べてみましょう。あなたの家づくりにも取り入れてみたくなるかもしれませんよ。
セントラルヒーティングで効率的に温まろう

セントラルヒーティングという言葉は、日本語で言うと全館集中暖房などとも呼ばれており、その仕組みは建物の中に一か所ボイラーなどの熱源を発生させる装置を置いて、そこで発生した熱を必要とされる各部屋へ送る暖房システムになります。北海道や寒い地域にお住まいの方はひょっとしたら聞かれたことがあるかもしれませんが、本州や暖かい地方に住んでいるとあまり馴染みがない暖房システムだと思います。最近広まりつつあるセントラルヒーティングですが、なぜ採用されているのかというと、ひとつには本州であっても、家庭内で起こる「ヒートショックによる死亡事故の増加」です。
日本では昔から局所暖房が主流でしたから、セントラルヒーティングを設置するノウハウを持っておらず、また初期費用が掛かるものに対しては敬遠されていたという事もあるでしょう。その結果、冬になると、暖かい室内から急に寒い廊下へ出る、暖かい浴室から急に冷たい洗面室へ出る、等のタイミングでヒートショックを起こす事例が増えているわけです。セントラルヒーティングであれば、家中に暖かさが広がりますので、家に入った瞬間玄関から暖かいという状況になり、家の中に気温差はほとんどありません。このことは快適に過ごすというメリットだけではなく、人の生死にも関わる大事なことですよね。最近はノウハウも確立され、様々なメーカーがセントラルヒーティングを販売していますので色々特色を見ながら選ぶことも可能になっています。
セントラルヒーティングの方法
セントラルヒーティングの方法その1.温水式セントラルヒーティング
セントラルヒーティングの種類は大きく分けて2つあり、その一つが温水式セントラルヒーティングです。家の中の一か所で暖められた「温水」を建物内部に張り巡らせたパイプを通して各部屋に設置されたパネルまで届け、暖かさを循環させるという方法です。熱損失が少なく、大きな建物にも対応できることから、現在ではこちらの温水式セントラルヒーティングが主流になっています。
セントラルヒーティングの方法その2.温風式セントラルヒーティング
もう一つのセントラルヒーティングの種類としては、温風式セントラルヒーティングがあります。こちらは熱源によって温めた「温風」をやはり、建物内部に張り巡らせたパイプを通して、各部屋に設置された吹き出し口から温風を届けるという仕組みです。温水に比べると温風の方が熱損失が大きく、小さい建物にしか使えないという事と、熱損失が大きいことでコストアップにつながるという事から温風式セントラルヒーティングは近年あまり主流ではないようです。
セントラルヒーティングを導入するメリット
メリットその1.家全体が暖かい
セントラルヒーティングのメリットの1つ目は何といっても、家全体が暖かいという事でしょう。玄関を開けた瞬間から暖かいという事ですから、寒い季節には本当に幸せですね。北海道の人は冬でも半袖で過ごすという事も聞いたことがありますが、それもセントラルヒーティングシステムのおかげでしょう。夜タイマーを掛けて夜中に寒くて起きたという経験がある方も少なくないと思いますが、セントラルヒーティングならそんな心配もありません。家の中でヒートショックが起こることがないという事も家族にとって安心のメリットです。
メリットその2.日々のメンテナンスが簡単
セントラルヒーティングのメリットの2つ目は、日々のメンテナンスが簡単な事です。エアコンのようにフィルターを掃除する必要はなく、パネルの埃をとる程度のお手入れで済むという事なので安心ですね。また、耐久性も他の暖房器具に比べると高く、熱源と各部屋のパネルの部分が別々になっているので万が一調子が悪くなっても各部分でメンテナンスをすることが出来るので、エアコンのように壊れたら買い替えなければいけないという事にはなりませんので、その分安く済みますね。
セントラルヒーティングを導入するデメリット
デメリットその1.暖房しかできない
セントラルヒーティングのデメリットの1つ目は、暖房しか出来ないという事でしょう。エアコンは部屋に一台つけてあれば、夏は冷房、冬は暖房というように一年中使えますが、セントラルヒーティングを取り入れた場合は、夏の冷房については別で考えなければいけません。北海道では夏に冷房を使わない家庭が多いという事ですから北海道でセントラルヒーティングが多く取り入れられているという理由も納得ですね。
デメリットその2.初期、運用コストがかかる
セントラルヒーティングのデメリットの2つ目は、コストに関することです。まずは初期費用について。ファンヒーターやストーブなどは本体を買えばそれで終わりですが、セントラルヒーティングの場合、熱源となるボイラーと、各部屋に置くパネル、またそれをつなぐパイプも必要です。さらに、それらを繋ぐためパイプなどは床下などの家の内部を通す工事も必要となります。また、一度稼働させるとシーズンオフまでは24時間つけっぱなしになりますのでランニングコストも高くなる傾向にあると言えます。
セントラルヒーティングの上手な使い方
上手な使い方その1.窓際に設置しよう
セントラルヒーティングシステムで設置されるパネルは、窓下に設置されていることが多いのですが、ヨーロッパの家の写真などを見たことがある方にはなんとなくピンとくるかもしれません。それは何故かと言うと実に合理的で、窓は家の外の冷たい空気を一番室内に通す場所だからなのです。室内に入ってきた冷たい空気を暖かいパネルの暖気によってすぐに暖めることで、室内に冷気を感じさせないという理屈という事になります。さらには窓の結露防止にもなるという事で、一石二鳥という訳ですね。
上手な使い方その2.設定温度を低めにする
皆さん例えば冬の寒い時、エアコンの暖房温度は何度くらいに設定していますか? 寒い外から帰って来た時や、朝起きて寒いリビングに入った時等、暖房温度マックスで風速も最強にして部屋を暖めていないでしょうか。セントラルヒーティングであれば、24時間つけっぱなしですので温度を低めに設定することが出来て、光熱費もお得になります。セントラルヒーティングとは言っても、各部屋に設定温度を変えられるパネルも付いていますので、部屋ごとに自分たちの気持ちの良い温度に設定するといいでしょう。
セントラルヒーティングを使う上で気を付けるポイント
気を付けるポイントその1.高気密高断熱で効率よく
セントラルヒーティングシステムとセットに考えて欲しいのが、家の高気密高断熱化です。セントラルヒーティングでせっかく温めた空気を外に逃がすような作りの家だと暖房効率も悪く、光熱費も上がってしまいますよね。家の壁には断熱材を付ける事が出来ますが、窓にも断熱効果が期待できるペアガラスなどを採用するといいでしょう。
気を付けるポイントその2.乾燥に気を付ける
エアコンやファンヒーターの場合、温風が直接出てきますので、風を人の体に直接感じることもあり、不快に感じる人もいるでしょう。また、セントラルヒーティングに比べると乾燥しやすいという事も言えます。ただ、セントラルヒーティングであっても温度が上がると、ある程度乾燥するのは仕方がないことです。温度を高く設定し過ぎないことと、必要に応じて加湿器などで対応しましょう。
後付けする時はリフォーム代に注意

セントラルヒーティングにするには、今ある自宅にリフォームで取り入れるという事ももちろん可能です。ただ、設置するためにはいくつかのハードルがあります。まず、ボイラーを設置するスペースが必要な事、家中を張り巡らせるパイプは大体が床下を通すことになりますが、床下の仕様によっては床材を剥がす必要があるなど、その際に必要となる工事や設置場所の確保などは、色々と打ち合わせが必要ですので見積もりを依頼することが大切ですね。
設計段階でセントラルヒーティング導入を検討しておけば、困る事も少ない
セントラルヒーティングは家族の健康の為にも、冬の間の室内での快適さを求めるためにも、是非取り入れたいと思う暖房システムだと思います。昔から日本の家づくりの基本は、夏の暑さと湿気対策として、夏を中心に考えてきたという歴史がありますので、いきなり冬を中心に考えるというのもピンと来ないかもしれません。でも、考えてみると日本には四季があるのですから、寒い冬も快適に過ごす方法があるなら、そうしたいですよね。夏の熱中症対策は自分たちの工夫次第でどうにかなることがありますが、冬のヒートショックについてはやはり家の中の環境を変えるという事をしなければ、防ぐことは難しいと言えそうです。家族が長く暮らしていく家づくりにおいて、最初の段階から暑い夏の事も寒い冬の事も両方考え、セントラルヒーティングを作りたいという決断をすることが出来れば、コストバランスも考えてすすめることができるでしょう。
まとめ

さて今回は、セントラルヒーティングシステムについて、色々と調べてみました。家中どこに居ても快適な温度で過ごすことが出来るこのシステム、なんとなく一部の寒い地域のシステムかなと考えていた方も、冬を快適に過ごす暖房器具の選択肢の一つになると思われたのではないでしょうか。コストの事や、室内環境の事など、メリットデメリットをよく検討し、家族が暮らしやすい家の為になると思ったら、是非お近くのプロに相談をしてみてください。

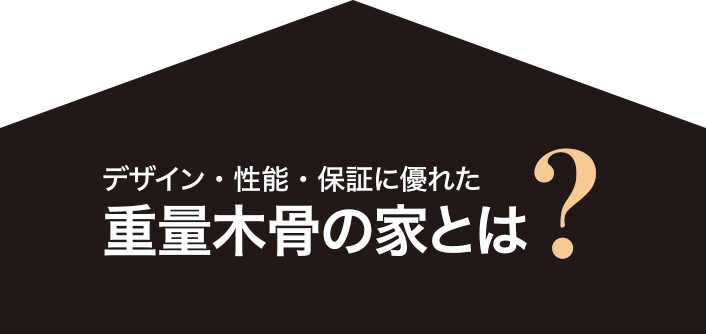










 はこちら
はこちら