バリアフリーの注文住宅で高齢者になっても住みやすい7つのポイント解説

バリアフリーの注文住宅で高齢者になっても住みやすい7つのポイント解説のインデックス
家は、自分の代だけではなく子供の代にも引き継がれていくことも多いものです。次の代に引き継ぐまでの間、新しい生命の誕生もあれば、どなたかの老化・介護というシーンが巡ってくるのは自然なことです。
このことを考えると、誰もが使いやすい「バリアフリーの家」はとても便利です。高齢者になってからも住みやすい家は、誰にとっても使いやすい家です。では、バリアフリーの家はどうやって作ればよいのでしょうか。家を建てるときから意識しておくとよいことをご説明します。
1.高齢者になってからも住みやすい「バリアフリーの家」とは?
バリアフリーとは、高齢者や障がい者などを含む全ての人が、生活するうえで支障となるものを取り除くことを指します。では、バリアフリーの家を作るにはどうしたらいいでしょうか。そのポイントは3つあります。
1-1.段差を解消する
まず一番目のポイントは「段差の解消」です。車椅子で移動する場合はほんの数センチの段差であって大きな障害になります。また、段々体の自由が利かない高齢者にとっても、段差がないというのは家の中での動きが楽になるでしょう。
1-2.転倒を予防する事
次のポイントとしては「転倒を予防する事」です。先ほどの段差をなくすことに加えて、手すりを付ける事で転倒のリスクはかなり減るはずです。手すりを設置した方がいい場所としては、歩行中に転倒の可能性のある廊下、靴の着脱などでしゃがみ込む玄関、腰をかがめる必要があるトイレ、どうしても段差の解消できない浴室等があるでしょう。
1-3.温度差をなくす事
そして最後のポイントになるのが「温度差をなくす事」です。ヒートショックという言葉はもうみなさんご存知だと思いますが、部屋と廊下や部屋‐部屋間の温度差をなくす事で体に与える影響を最小限に抑えることが出来ます。また、建物内の温度差を少なくする事は結露やカビの発生なども抑えることが出来るので家の長寿命化にもつながります。
このように、バリアフリーの家は、高齢者や障害のある人にとってはもちろん、家族全員にとってもメリットがあります。例えば妊婦さんがつまづかずに済みますし、若年であってもケガや病気で、室内で車椅子を使わざるを得なくなることもあるからです。
2.バリアフリーの家の作り方、ヒント7つ
高齢者になってからも住みやすいバリアフリーの家は、段差だけでなく、他の部分での工夫も大切です。次のような部分での工夫も、後々「よかった」と思えるはずです。
2-1.トイレ―寝室のそばに配置、広めにつくる

寝室そばにトイレを作っておけば、高齢者になってからも住みやすい家を実現できます。年齢を重ねると夜間にトイレに行く頻度が増えますし、夜間は転倒のリスクが高まります。また、ヒートショック(温度差による心臓麻痺などの身体的トラブル)が気になる季節にも寝室そばのトイレはとてもうれしいつくりです。
もしも家の中にトイレを1箇所しか作れないときは、寝室から直接入れる位置におき、他の面の壁にもドアを設けて、洗面や脱衣室からも入れるよう「2ドア」にするのもよいでしょう。水周りを連続させることで、トイレ・洗面・入浴がひとつの線で結ばれますので、動きも少なくてすみ、高齢者になってからも住みやすい家となります。
トイレの広さは、車椅子に乗った介護される人と介護者が入れるようなスペースであることが理想的ですし、手すりは必ずつけましょう。手すりはL字型で便座の左右に配置することで介護される人と介護する人の両方が使えます。便座は暖房便座が望ましいですし、トイレ内に暖房器具を設置してヒートショックを防止することも大事なポイントです。出入口はもちろん車椅子が通れる大きさにする必要がありますね。
2-2.洗面―高さに注意、ベンチを設けても便利
洗面台を作るとき、高さに注意してください。健康な方が立って使用するのによい高さと、車椅子生活になった方が座った状態で使いやすい高さはかなり異なります。最初から車椅子生活を想定した高さで作っておくのはいかがでしょうか。健康な大人には少々低いかもしれませんが、お子さんや高齢者・車椅子の方にはとても便利です。
洗面台の下部にも工夫を凝らす事ができます。車椅子のまま洗面台に近づけるよう、下部の収納スペースを取り払った洗面台が便利です。まだまだ車椅子は先、という方であっても、長時間立っていることがつらいこともあるでしょう。これを解消するため、洗面そばにベンチを設置したり、イスを置けるスペースを確保しておくのもよいことです。
2-3.リビング・ダイニング―だれもが集まれる工夫を

リビングやダイニングは、家族が顔を合わせる場です。高齢者を含む家族全員が自由にくつろげる場にするためには、いくつかの方法があります。
ひとつ目は、テーブルの高さです。テーブルに車椅子のまま入れる高さは約70センチが目安です。一般的なテーブルも同じく約70センチですが、車椅子のサイズによっては入れないこともありますので、高さ調節のできるタイプのテーブルを選ぶと良いでしょう。もしも造作テーブルを依頼するときも、この点に注意をすれば、長く使えるものになります。
また、リビング・ダイニングの一部に畳敷きの小上がりを作り、そこにテーブルを寄せられるよう工夫するのはいかがでしょう。イスに慣れない方、高齢となりイスに座ることが面倒になってしまった方も含み、家族全員で食卓を囲むことができます。このようなスペースを作るときも、車椅子と小上がりとの差が小さいほど移動が楽になります。
小上がりは、ご高齢の方が食事中に疲れたとき横になることもできますし、お子さんのお昼寝やお遊びの場所にもなりますので、育児中の親御さんにも安心を与えてくれます。
2-4.廊下―車椅子の通行ができる幅にし、手すり設置を見越して
高齢者になってからも住みやすい家に必要でありながら、バリアフリーリフォームがしづらい部分に廊下があります。廊下は介護者と介護をされる方が二人並んで歩ける幅に、プラスアルファの広さが必要です。
誰かに頼れば歩けるうちは二人分の幅で大丈夫ですが、いったん車椅子での生活が始まれば廊下の幅はさらに広く必要です。車椅子のサイズにもよりますが、最低でも廊下の幅は90センチ必要です。これはあくまでも進むだけ・戻るだけの「一方通行」のケースであって、もしも廊下で方向を変える(回転する)ことまでを考えれば150センチ以上が必要です。
将来は手すりをつけたいと考えているのであれば、それを見越して壁に手すり用の「下地」を入れておくとよいでしょう。リフォーム時に大掛かりな工事にならずにすみます。
また、床材にも注意が必要です。車椅子で傷が付きにくい丈夫な材質を選ぶこと、また転倒防止のためには滑りにくい素材であることも重要です。また夜間の移動の事も考えて足元ライトなどを壁に設置しておくのもよいでしょう。
2-5.玄関―スロープを作っておく
家の内と外をつなぐ玄関部分も、高齢者になってからも住みやすい家とするための大切なポイントです。杖をついて歩くとき、階段はとても怖いものとなります。また、段があれば車椅子での出入りはとても難しいものです。最初からスロープをつけておけば、ご高齢の方のみならず、妊婦さんやお子さんにも安心ではないでしょうか。
玄関スロープは意外にスペースを必要としますので、家作りに着手した段階から組み込んでおくか、ないしは玄関ポーチに後付けできる広さを確保しておくと安心です。
玄関扉も工夫が出来るポイントです。開き扉タイプではなく引き戸のタイプにすることで出入りの時に動きがスムーズになります。そして上がり框の高さにも注意しましょう。通常の家ですと20-30cmぐらいが標準になりますがバリアフリーの家を作る際には11cmぐらいが限度と考えてください。また、靴の着脱の際には手すりがあると便利ですし、ベンチを設置することでかがむ必要がなくなりますので動きが楽になりますね。
2-6.キッチン―高さ調節できる製品を
健康なうちは立って調理もできますが、疲れたり足腰を痛めたりしたとき、一時的にイスに座って調理をすることがあります。さらに加齢によって調理そのものに時間をかけたくなくなったときは、座ったまま調理ができるキッチンが便利です。
このことを事前に見越して、高さ調節のできるキッチンを設置するのはいかがでしょうか。少々お値段は高くなりますが、高齢者になってからも住みやすい家になることは間違いありません。また、小さなお子さんがお手伝いをしたくなったときや、仕事のサイクルで身長差のあるご夫婦が交互にキッチンに立つときにもとても便利です。
キッチンそのものを上げ下げするのではなく、床部分を上げ下げする方法もありますので、家作りの相談の際に要望しておくとよいでしょう。
2-7.バスルーム―介護者と一緒に入れる広さとすべり止めを
高齢者になってからも住みやすい家は、水周りの使い勝手がとても重要です。特に身体の清潔を保つバスルームはその代表です。浴槽の立ち上がり部分で足をとられ、転んでけがをする可能性がありますので、脱衣室と浴室の段差をなくすようにしてください。また、広さに関しても、介護される人と介護する人の二人で入れるような広さと出入り口の幅が必要です。
さらに、バスタブや床は滑りにくい素材を選びたいものです。滑りにくくやわらかい素材はお子さんが小さなときにも安心です。浴槽に関しても段差は少ない方がいいですが、カラダが温まる程度の深さは必要なので、介護される人の体の大きさなども考えて検討する必要があります。さらには車椅子生活になったときのために、シャワー用車椅子で直接入れるように間口を広くとっておくことも考えておくとよいかもしれません。
3.バリアフリー住宅の間取りのコツ
バリアフリー住宅を作る際に、間取りについて以下のポイントに留意することが重要です。これらのポイントを考慮してバリアフリー住宅を作ることで、さまざまなニーズに対応し、快適でアクセスしやすい住宅で生活することができるでしょう。
3-1.移動しやすい動線を考える
バリアフリー住宅においては、移動しやすい動線というのが、まずはポイントになります。介助者と介護者が一緒に移動したり、車いすで移動することを考えると、平面的には広い通路幅と開口幅が重要です。また、建具の付け方にも工夫が必要でしょう。開き扉よりも引き戸の方が、開け閉めの際に移動が少なくて済みます。さらに、手摺を適切な場所に設けたり、適度な明るさの照明を設置する事は、介護される前であっても、自立して生活するために必要な事でしょう。
3-2.平屋がベストだが、2階建ての場合は移動方法を考えておく
2階に介護者が生活する空間がある場合は、エレベータの設置を検討しておくといいでしょう。エレベーターのサイズについても、車椅子に対応できるようなものを設置する必要があります。エレベーターの設置が難しい場合は、階段に取り付ける昇降機や、階段の幅を広くする等、なるべく上下の移動の際の負担を減らす工夫が必要です。また、家の中で上下の移動をなるべく少なくするために、寝室、リビング、水回りなども全て同じフロアに設置できるようにしておくといいでしょう。
3-3.廊下はできるだけ短めに
バリアフリー住宅で暮らす介護者にとって、一番負担になるのは移動することです。この移動距離をできる限り少なくするために、廊下はなるべく短くしましょう。寝る、食べる、トイレに行くなどの機能が近くにある事で、よりストレスなく、快適に過ごすことが可能になります。廊下をなるべく少なくすることは、異なる居住空間同士が近づくことになりますので、他の家族との距離も近づきます。これによって、介護者が精神的に安心感を得ることができます。
3-4.室内外の床材選び
バリアフリー住宅において、床材の選定は非常に重要なポイントでしょう。実は家の中での事故というのは非常に多いので、段差によるつまずき、歩行中に滑って転倒してしまうなどが、起こらないような床材を選定しましょう。室内で歩行する際には、肌に優しい素材や、床暖房などの設備に対応している素材、光が反射しにくい素材など、考慮すべきポイントは多岐に渡ります。室外においては、風雨や太陽光に晒されますので、耐久性も必要ですし、水に濡れた時に滑りにくいという点も、重要なポイントでしょう。
4.「誰でも生活しやすい」を意識して、バリアフリーの注文住宅を建てる
実際に、バリアフリーを取り入れたお宅をご紹介いたします。バリアフリーにすることで、家族みんなが快適に暮らせる家が実現できることをご理解いただけるのではないでしょうか。
4-1.段差をなくした玄関は家族みんなに優しい
上がり框の段差がほとんどないバリアフリー玄関。踏み台を設置しているので、これを利用すれば、ほとんど段差を感じないで移動が出来そうです。足の上げ下ろしが辛くなってくる世代にも優しいですし、小さなお子さんがいても快適なつくりと言えます。また、車椅子も十分に置ける広さがあるので、他の家族や介護する人が居ても外出の際に窮屈に感じる必要もなくも安心ですね。
4-2.部屋の移動も段差無しでスムーズに
和室とリビングの間、リビングと廊下の間は段差をなくして移動をスムーズにしています。廊下とリビングは天井までの引き戸が設置されているので、車いすでの移動もスムーズに行う事が出来るでしょう。年々、座ったり立ったりという動作が辛くなってくることも考えられますので、和室に合う椅子などのインテリアも考えてコーディネートしてみるのも楽しいですね。
4-3.バリアフリーでもデザインには力を抜かない
こちらは洗面とトイレが一体になったバリアフリーの水回りスペースです。バリアフリーと言うとデザイン性は二の次になってしまうのではと思いがちですが、このようなカッコいいバリアフリー仕様も素敵ですね。洗面台には椅子を設置することでゆったりと座ってお化粧や身支度が出来そうです。
4-4.バリアフリーでも庭を楽しむ
庭との段差は仕方がないですが、段差をなるべく低くして、手すりを付けることによって出来るだけバリアフリーに近づけて庭を楽しむことも可能です。また、テラスまでは段差を感じずに出ることが出来ますので、車椅子であってもテラスまで出て、庭の緑を近くに感じるだけでも気持ちのいい時間が過ごせますね。
4-5.全てを引き戸にし、バリアフリーで過ごしやすく
こちらの事例は、将来のことを見据えて1階をバリアフリー住宅にするべく、扉を全て引き戸にしています。引き戸は、開閉するときに人が移動する必要がありませんので、省スペースになるというのがメリットです。また、開閉する際に力を必要としません。開き戸は、開閉の際に前後の移動が必要ですし、握り球を握って回転させるという力も必要になるので、それらの点を比較しても、引き戸のメリットはありますよね。
4-6.和室までフラットに移動できる広々LDK
こちらの事例は、LDKと一体になった、和室空間まで全てがフラットで移動できる、バリアフリー住宅の一例と言えます。また、空間に置いてある物も少なく、移動するためのスペースが広く取れる為、介護者と介助者が一緒に移動したり、車いすで移動する際にも十分余裕をもって動くことができるでしょう。また、キッチンで作業しながら和室まで全てを見通すことができるので、万が一家族に異変が起きても対応しやすいというのも安心です。
4-7.将来の暮らしやすさを見据えてバリアフリーに
家づくりは、それぞれのタイミングで実現したい暮らしも違ってくると思いますが、ある年齢に達すると将来のことを考えて、バリアフリー住宅にするかどうかも視野に入ってくるのではないでしょうか。そういった意味では、こちらの事例は、平屋+ロフトという空間構成になっているので、将来にわたって長く暮らすための対応も楽になるでしょう。1階は全てバリアフリーの一室空間ですので、広々使うことができますね。
5.住まいをバリアフリーにする際の補助金や減税制度
高齢化社会を見据えて、国や自治体でもバリアフリー住宅を支える補助金や減税などの制度があります。お住いの自治体によって制度が違ったり、また期間が決まっている補助金などもありますので、建築会社に相談して賢く活用しましょう。
【リフォーム】介護改修補助金
厚労省が制定している介護保険の中で、特定のリフォームをする際に最大20万円までの工事において、18万円までの補助金が下りる制度があります。対象となるリフォーム工事には、家の屋内外において手すりを取付ける、段差を解消する、扉を引き戸に変更する、床を滑りにくいものに変更する、便器を洋式に変更するなどがあります。これには、要支援、要介護者である認定が必要になるので、自分がこの制度を活用できるかどうかは、まずはケアマネージャーに相談することから始めるといいでしょう。
【リフォーム】固定資産税の減額
「バリアフリー改修工事にかかる固定資産税の減額措置」という国の定めた制度があります。新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額されるというものです。
リフォームにおける減税措置なので、建築後10年以上経過した住宅に限られてきますが、こういった情報があれば将来リフォームする際に活用できるので、知識として覚えておくといいですね。他には、住宅特定改修特別税額控除というものがあり、これは、バリアフリー改修工事をした場合、所得税が減税されるというものになります。
まとめ
高齢者になってからも住みやすい家とは、「バリアフリー」なつくりです。これは高齢者だけでなく、誰であっても使いやすい家です。家族そろって無理なく楽しい暮らしをしたいのであれば、はじめからバリアフリーにする、もしくは将来のバリアフリー化を見越した家づくりをしたいところです。
バリアフリーな家は、住まう方の状態により必要なものが異なることも注意点のひとつです。手すりひとつにしても介護される方の身長に合わせなければなりません。車椅子のサイズを考慮する事も必要です。さまざまなケースに対応できるよう、家づくりをスタートさせた段階で、柔軟に対応できる家を作っておくことが何よりも重要なことです。

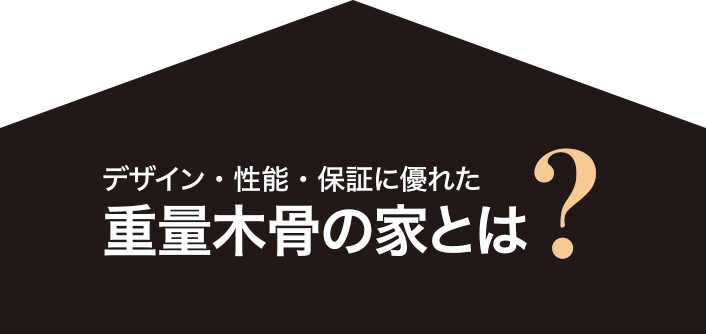























 はこちら
はこちら